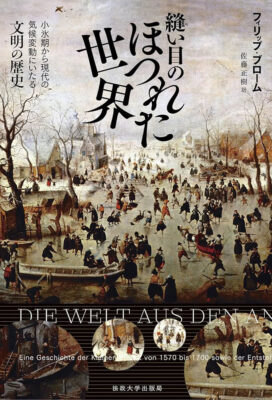フランスの経済学者・哲学者セルジュ・ラトゥーシュが2020年に発表した『脱成長と食と幸福』は二部構成で、「幸福」と「食」というトピックを通して「脱成長」を論じている。
本書を読み出すとすぐに、個人的に非常に興味をそそられる記述に出くわす。それはたとえば、序章で、本書の関心のひとつとして挙げられている、啓蒙の時代における幸福(bonheur)という観念の出現からその経済学的還元(「一人当たりGDP」)に至る過程である。あるいは、第1章の導入部にある「幸福の意味の大転換をよく理解するためには、この還元を可能にした倫理の大転換こそ明らかにする価値があるのだが。この倫理的転回は、西洋文明では十六世紀から十七世紀にかけて起こったのである」という記述だ。
そうした記述から筆者が思い出すのは、しばらく前に読んだ歴史家フィリップ・ブロームの『縫い目のほつれた世界 小氷期から現代の気候変動にいたる文明の歴史』のことだ(以前の記事「小氷期(16世紀末~17世紀)ヨーロッパの劇的な変化を描くフィリップ・ブロームの『縫い目のほつれた世界』は、アミタヴ・ゴーシュの小説『Gun Island』の視点と深く結びついている」参照)。
そこには16世紀末から17世紀にかけて、小氷期の寒冷化に見舞われたことを発端として、農業、戦争、交易から天文学の発見や啓蒙主義まで、劇的な変化を遂げていくヨーロッパの姿が詳細に描き出されている。
農業では凶作によって、地域の規則に従う必要がない遠隔地貿易が強化された。大農場の土地が整理され、市場を当て込んだ生産が行われ、利益本位の商業活動が活発になり、伝統的な生活様式や慣行が排除され、中産階級が台頭し、追い払われた小農は都会に仕事を見つけるしかなくなった。戦争では、新たな技術と兵法が導入され、農業生産だけでは戦費を賄いきれなくなり、商業と手工業に頼るようになり、重商主義が発展し、戦争を支援する。貧しい人々は安い労働者として国内産の原料を高価な輸出品に変える使命を担う。
そして、気候変動に端を発した17世紀の衝撃から新しい知識の領域が開け、啓蒙主義や合理主義が発展する。「ここで決定的に重要だったのは、スピノーザとロックとの異議申し立てだった。二人のいう普遍妥当な人権という理念は、集団の権利に比べて個々人の権利を強化するものだったため、それまで道徳にかなう秩序だとみなされてきたものをひっくり返した」
ラトゥーシュの『脱成長と食と幸福』が個人的に興味深いのは、こうしたヨーロッパの劇的な変化とその後を、「幸福」という観念を軸に読み直していることだ。長い引用になってしまうが、以下の記述は、啓蒙の時代の決定的な転回と現代がどうつながっているのかがよくわかる。
「幸福は、一人当たりGDPによって測定される物質的な豊かさとして現われた。すでに指摘した通り、この意味での幸福の出現は、倫理の根本的転換がなかったならば起こらなかっただろう。過剰に発展した近代では、倫理の侵犯は社会体制として確立している。だが、その起源は啓蒙の時代に起こった決定的な転回に求められる。さらにこの倫理的転回自体は先行する宗教改革によって準備された。西洋社会は人類史のなかでただひとつ、他のすべての人間社会が抑制しようとしたもの(大なり小なり成功した)を解き放った社会である。西洋社会が解放したのは、つまり、スピノザの言う「悲しい情念」(野心、貪欲、妬み、恨み、エゴイズム)やフロイトの言う「攻撃的な情念」(その意味はスピノザの概念に近く、「文明のなかの不満」を生じさせる)である。後期近代の現代西洋社会では、ある種の逆説的な(もっと言えば二律背反的な)倫理が侵犯されるまでに至っている。マックス・ウェーバーが主著『プロテスタントの倫理と資本主義の精神』で示したように、宗教改革は強力な個人主義を導入し、資本主義の精神、特にその清教徒版をいつの間にか普及させた。しかし、倫理の大逆転をもたらしたのは、バーナード・マンデヴィルとその主著『蜂の寓話』である。私的な悪徳が蜜蜂の巣の繁栄をもたらすというこの寓話の結末は、当時醜聞に近い反響を喚起した。しかし、アダム・スミスの「見えざる手」を経由して、マンデヴィルの思想は次第に西洋社会の無道徳的信条となった(非倫理的信条とさえ言える)。経済活動によって推進される私的な悪徳が利益を通じて公共の美徳に転じ、経済主体のあずかり知らぬところで共通善の生産に寄与する――近代はそう信じてきたし、今なおそう信じ続けている(あるいは信じているふりをしている)。その結果、人々は何の危険もなく悪徳を解き放つことができた。いやむしろ解き放たねばならなかったのだ。ビジネス・スクールでは、リバタリアニズムの容赦ないスポークスマンであるアイン・ランドに倣って「貪欲は良いことだ(Greed is good)」と教えられるが、それは今述べたような思想史的背景があるからだ」
しかし、「幸福」という観念を軸とした読み直しに注目するためだけに、ここでブロームの『縫い目のほつれた世界』を取り上げたわけではない。
たとえば、『脱成長と食と幸福』の第3章には、脱成長のための具体的な十項目の政策が提示されている。それを列記すると以下のようになる。
「1、持続可能なエコロジカル・フットプリントを再生する。/2、適切な環境税の実施によって外部コストの内部化を行ない、輸送を削減する。/3、諸活動の再ローカル化を推進する。/4、小農民の農業を再生する。/5、生産性の増加分を労働時間の短縮と雇用創出に割り当てる。/6、関係財の「生産」を促進する。/7、エネルギー消費を現行水準の四分の一まで削減する。/8、メディアにおける広告スペースを大胆に制限する。/9、科学技術研究の方向を見直す。/10、お金の再領有化(再ローカル化)を進める」
『縫い目のほつれた世界』で浮き彫りにされる17世紀ヨーロッパの激変が頭に入っていると、こうした変革を実践するために、「現行の社会機構と根本から決別」することの意味がより鮮明になる。と同時に、変革がいかに困難なものであるのかも想像される。
ここで再度『縫い目のほつれた世界』を振り返ると、啓蒙主義思想によって根拠を与えられ、成長した西欧社会は重大な矛盾を抱え、今日にいたってなおそれを克服できずにいる。社会を動かす中産階級の経済面での成功と富貴とは、17世紀のもうひとつの遺産である搾取に支えられている。その搾取は、啓蒙主義のもろもろの要請と絶対に相いれない。そこから対立が生まれ、今日までつづいている。ブロームはそれを、「自由主義の夢」と「権威主義の夢」というふたつの夢の対立としてとらえられている。
それを踏まえると、『脱成長と食と幸福』においても、変革にとって障壁となるものについての言及を強く意識せざるをえなくなる。たとえば、以下の記述だ。
「企業のロビー活動は、国家の加担、また多くの場合、多国籍企業から研究助成を受ける御用学者の加担を常にあてにしている。利益追求のあまり、科学者たちによる多くの警鐘(アスベスト、アフラトキシン、フィプロニル、イミダクロプリド、ヘパリン、電磁場、ダイオキシン、内分泌かく乱物質、環境ホルモン)が政府当局によってもみ消され、関連研究所の予算が削減され、さらには(雇用を「守る」ために時には労働組合が加担して)責任ある科学者の免職が行われたことを思い出すとよい」
さらに、以下の警鐘も胸に刻む必要がある。
「脱グローバル化を切望するさまざまな声は、どれも正当な理由をもっている。だが、その声は、経済成長想念の脱植民地化を伴わなければ、トランプ、オルバン、ボルソナロのような排外主義的なポピュリズム運動の首謀者とその仲間たちの道具として利用される危険がある。彼らは待ち伏せている」
その待ち伏せが、いまではとんでもなく厄介なものになっている。たとえば、『脱成長と食と幸福』には、食品廃棄に関して以下のようなデータが紹介されている。
「(前略)このため、カルロ・ペトリーニが述べるように、世界で生産される食べ物の三〇~五〇%、すなわち毎年一二億~二〇億トンの食糧が、人間の胃袋に決して届くことはないのだ。
肥満、コレステロール、糖尿病、癌、ストレス……このフード・システムの健康に対する影響が悲劇的であることは、いくら語ったとしても十分ではないだろう。世界には八億四五〇〇万人が飢餓に苦しみ、六億人が肥満病を患っている。これら二つの統計を付き合わせると、経済成長社会のあらゆる不条理が食品産業の分野にまで及んでいることがわかる」(※カルロ・ペトリーニはスローフード運動の創始者)
これは間違いなくゆゆしき問題だが、事実よりも感情が優先され、イデオロギーが台頭するポストトゥルースの時代には、そんな現実でさえもないがしろにされる怖れがある。
《参照/引用文献》
● 『脱成長と食と幸福』セルジュ・ラトゥーシュ著、中野佳裕訳(白水社、2024年)
● 『縫い目のほつれた世界 小氷期から現代の気候変動にいたる文明の歴史』フィリップ・ブローム著、佐藤正樹訳(法政大学出版局、2024年)
[amazon.co.jpへ]
● 『脱成長と食と幸福』セルジュ・ラトゥーシュ著、中野佳裕訳(白水社、2024年)
● 『縫い目のほつれた世界 小氷期から現代の気候変動にいたる文明の歴史』フィリップ・ブローム著、佐藤正樹訳(法政大学出版局、2024年)