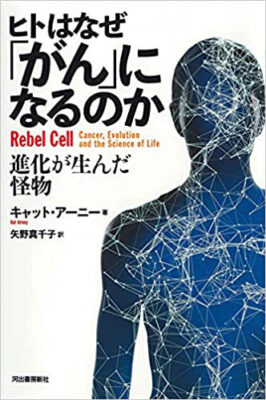サイエンスライター、キャット・アーニーが書いた『ヒトはなぜ「がん」になるのか――進化が生んだ怪物』(2020年/邦訳2021年)の「はじめに」には、がんに関して本書のポイントとなるような指摘が列挙されているが、そのなかでも特に注目したいのは、以下のような記述だ。
「科学者たちはがんの進行を、自然界の生物進化の縮図として見るようになってきた。生物が突然変異で新しい形質を得たあと、その形質が自然選択で選ばれれば生き延び拡散するのと同じように、がん細胞も新しい変異を拾ったあと、自然選択で選ばれれば増殖して拡散する。ダーウィンが描いた進化系統樹のように、がん細胞も枝分かれしながら進化する。ここで私たちは、がんについてのもう一つの不都合な真実、治療自体ががんの悪性化に手を貸すという真実を知ることになる。
がんが育つとき私たちの体の中で働いているのは、地球上の生物進化を駆り立ててきたのと同じプロセスだ。がんの進化における自然選択の選択圧は、本来なら命を救うはずの治療薬という形でやってくることもある。薬は、その薬の効く(薬に反応する)細胞を死滅させ、薬の効かない(薬に耐性のある)細胞を栄えさせる。つまり、薬はがんを弱体化させるどころか増強させる。そうやって強力になったがんは再発という形で現れるが、そのときにはもう、何をどうしても止められなくなっている。進行したがんに現行の治療法が無力なのは不思議でも何でもない」
この記述を踏まえて読むとより興味深いのが、生態学者ロブ・ダンが書いた『ヒトという種の未来について生物界の法則が教えてくれること』(2021年/邦訳2013年)の第十章「進化とともに生きる」だ。その内容は、アーニーが提示するがんについての考え方に、生物進化の側から呼応しているともいえる。
第十章で最初に取り上げられているのは、数年前にハーバード大学のキッショーニ研究室で、マイケル・ベイム、タミ・リーバーマン、ロイ・キッショーニが行った「メガプレート実験」だ(この実験については、すでに一度、別記事「サイエンスライター、エド・ヨン(『世界は細菌にあふれ、人は細菌によって生かされる』)によるメガプレート実験の紹介と抗生物質に対する細菌の耐性進化への警鐘」で紹介している)。
「メガプレート実験」は、抗生物質に対する細菌の耐性進化のプロセスを調べる実験だ。ベイム、リーバーマン、キッショーニの3人は、幅60センチ、長さ120センチ、厚さ11ミリの巨大なシャーレを作り、帯状の9つの区画(カラム)に分割した。メガプレートと名付けられたこのシャーレに充填される培地は二層構造になっている。その下層は、細菌の餌となる個体培地で、インクで染められている。一番外側の両端の区画の個体培地には抗生物質はまったく含まれず、内側に向かうにつれて、抗生物質の濃度が1から10倍、100倍、1000倍と徐々に高まっていく。これに対して、上層は細菌が移動できる液体培地になっている。そのメガプレートの両端に、抗生物質に対する耐性を持たない大腸菌が放たれる。
大腸菌は、抗生物質が含まれていないカラムをすぐに覆い尽くす。それから数日後、最低濃度の抗生物質の存在下でも生存できる能力をもつ、最初の変異株が出現し、その細胞の子孫細胞が第二カラムに溢れ出し、黒い培地を覆い尽くし、白く染めていく。その次の数日間に、より高濃度の抗生物質の存在下でも生存できる能力を与える突然変異が起き、自然選択はそれらの変異株に有利に作用し、第三カラムに広がっていく。同じことが繰り返され、実験開始から約11日間で、巨大なシャーレの中央のカラムに薬剤耐性菌が押し寄せることになった。
ロブ・ダンは、このような耐性進化のストーリーが細菌だけに限ったことではないと断って、マラリア原虫などの原生生物の耐性進化に言及する。さらに微生物だけでは終わらないと断って、トコジラミや他の昆虫種の殺虫剤に対する抵抗性の進化にも言及する。そして、がん細胞についても。
「ヒトのがん細胞を殺傷するために、化学療法で使用される抗がん剤もやはり使用量が増している。がん細胞は、細菌や害虫とは全く違うように思うかもしれないが、がん細胞もやはり抗がん剤に対する耐性を進化させる可能性があり、そうなった場合には、抗がん剤に反応しない腫瘍、つまり抑えようとしても抵抗する腫瘍になってしまう」
さらに以下のような記述も。「ヒトの体内のがん細胞は、人体がまるでメガプレートであるかのように、勇ましい進化の物語を繰り広げる」
ところで、記事の冒頭で引用した「科学者たちはがんの進行を、自然界の生物進化の縮図として見るようになってきた」という記述では、この考え方が比較的新しいものであるような印象を与えるが、本文を読むと考え方そのものは以前からあったことがわかる。
1976年、フィラデルフィア生まれの科学者ピーター・ノウェルが一流科学誌『サイエンス』に「腫瘍細胞集団のクローン進化」と題する短い論文を発表し、がんは一個の細胞からスタートするが、変異と自然選択を繰り返しながら進化し、より攻撃的に、より治療に抵抗するようになる、と論じたが、その論文は注目されなかった。
▼ ピーター・ノウェルは、血液がんの一種である慢性骨髄性白血病で爆発的な細胞増殖を促している異常な染色体=フィラデルフィア染色体の発見者として名声を確立していたが、そんな彼が書いた論文「腫瘍細胞集団のクローン進化」は注目されなかった。
さらに2000年、インスティテュート・オブ・キャンサー・リサーチ(ICR)で小児白血病を研究してきたがん生物学者のメル・グリーヴスが『がん――進化の遺産』(邦訳2002年)という本を出版し、がんが進化と切っても切れない関係にあるという理論を展開したが、ノウェルのときと同様に注目されることはなかったという。
つまり、考え方そのものは以前からあったが、広く受け入れられることはなかった。「2011年の分析によると、1980年代以降に発表されたがんの再発または治療耐性に関する科学論文のうち、進化の概念に触れたものは1パーセントに満たず、その後の5年間で10パーセントになったものの、上げ止まっているという。この分析結果はある程度理解できる。いまでこそ、小さな腫瘍サンプルの遺伝子すべてを解読し、その進化経路をたどる作業を何百回、何千回とくり返せるようになったが、そこまでDNA配列決定技術が向上したのはここ数年のことだからだ」
この考え方を受け入れるのかどうかは、いまダーウィンの理論がどれだけの意味を持っているのかで決まるともいえる。
著者アーニーにとってグリーヴスの『がん――進化の遺産』は座右の書であり、彼女は、がんを進化視点で考えることがこれほど長く無視されてきた理由を探るために、もうすぐ80歳になるグリーヴスに会いにいったという。本書には、グリーブスの以下のような発言が引用されている。
「遺伝学やゲノム学は偉大です。複雑な変異の様相を解きほぐし、それらが単に順番に起こるのではないことを明らかにしてくれました。しかし、私たちはあまりに遺伝子中心の考え方に染まってしまいました。何がどう起こるのかの背景を考えれば、進化の考え方をもっと重視すべきです。腫瘍医の多くが薬剤耐性の背景を知ろうとしないことに、私は驚いています。誰でも知っているダーウィンの自然選択ですよ。それに気づくのに、どうしてこんなに時間がかかるのでしょうか」
アーニーは、そんなグリーヴスの発言に対して、以下のように考える。「がんには一発で仕留められるような定まった標的があるはずだと考える人たちに、がんは適応と進化をくり返す可変的で複雑なシステムだという概念に目を向かせるのは簡単ではない。おそらく、これまで『特効薬』を期待して多額の資金を投じてきた拠出機関や製薬会社には、いまさら古めかしいダーウィニズムなんかをもち出されても困るという気持ちもあるのだろう」
ロブ・ダンは『ヒトという種の未来について生物界の法則が教えてくれること』の第十章に「進化とともに生きる」というタイトルをつけ、メガプレート実験から話を始めた。彼はその実験について、あらためて確認するかのように説明をしている。
「メガプレート実験は、生物学の最も揺るぎない法則の一つである、自然選択による進化の法則の意味を考えさせ、それをリアルタイムで見せてくれる。自然選択による進化の法則とは、ごく簡単にいうと、多くの子孫を作ることのできる個体の遺伝子や形質は、子孫を少ししか作れない個体の遺伝子や形質よりも有利になる傾向があるということだ。自然選択による進化の法則とはつまり、ダーウィンが提唱した理論のことである」
キャット・アーニーは、『ヒトはなぜ「がん」になるのか』の「はじめに」の最後に、「これは、がんについての話ではない。生物についての話だ」と書いている。だから、がんだけでなく、生物学の最も揺るぎない法則の一つにも関心が持てれば、非常に興味深く読むことができる。
《参照/引用文献》
● 『ヒトはなぜ「がん」になるのか――進化が生んだ怪物』キャット・アーニー著、矢野真千子訳(河出書房新社、2021年)
● 『ヒトという種の未来について生物界の法則が教えてくれること』ロブ・ダン著、今西康子訳(白揚社、2023年)
● 『がん―進化の遺産』メル・グリーブス著、水谷修紀監訳(ブレーン出版、2002年)
[amazon.co.jpへ]
● 『ヒトはなぜ「がん」になるのか――進化が生んだ怪物』キャット・アーニー著、矢野真千子訳(河出書房新社、2021年)
● 『ヒトという種の未来について生物界の法則が教えてくれること』ロブ・ダン著、今西康子訳(白揚社、2023年)
● 『がん―進化の遺産』メル・グリーブス著、水谷修紀監訳(ブレーン出版、2002年)