先日、久しぶりにサワードウ・スターターを起こしてみたときに思い出していたのが、生態学者ロブ・ダンが2018年に発表した『家は生態系 あなたは20万種の生き物と暮らしている』のことだった。本書については以前にも取り上げているが(「自分たちの家のなかの生態系や微生物多様性を守り、豊かにし、健康的に暮らすには その2――ロブ・ダン著『家は生態系 あなたは20万種の生き物と暮らしている』」)、実はサワードウ・スターターも無関係ではない。最後のほうで、ロブ・ダンのチームが行ったサワードウ・スターターについての実験が取り上げられているのだ。
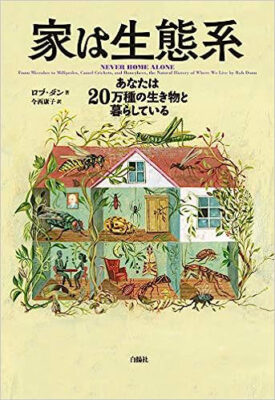
その実験のヒントになったのはキムチだ。韓国料理には、「手味」という重要な概念が体現されているという。たとえば、料理教室で先生と生徒たちが、同じ材料を使って、先生の手の動きをまねてまったく同じ手順でキムチをつくっても、数週間後、できあがったキムチの味にはそれぞれに微妙な違いがある。作る人の手が生みだした風味の違いがでる。そんな話を聞いたロブ・ダンは、キムチを作る人の身体やその家屋に棲みついている微生物が、そうした手味の一部を醸し出しているに違いない、と確信するようになった。
「キムチにはさまざまな種類の微生物が生きている。その一部は、白菜や大根そのものに由来すると思われる微生物だ。しかし、キムチには、人体の常在微生物として知られる微生物も含まれている。たとえば、ラクトバチルス属細菌はキムチの要であり、スタフィロコッカス属細菌(ブドウ球菌)もまたしかりである。ラクトバチルス属細菌はごく一般的な人体常在菌で、腸内細菌として知られている菌種や菌株もあれば、膣内細菌として知られているものもある。一方、ブドウ球菌は、ヒトの皮膚常在菌である。こうした属や種の細菌のそれぞれがさまざまな酵素や有機物を作り、風味を生み出している。出来上がったキムチの味に、それぞれが何らかの貢献をしている」
これをきっかけにロブ・ダンは、身の回りの微生物や身体に棲んでいる微生物が食品に及ぼす影響を解明する新プロジェクトを起ち上げようと考えた。では、初の大規模食品研究の対象にふさわしい食品はなにか。人体や家屋に棲みついている微生物と関わりがありそうで、しかも、シンプルで実験しやすく、なおかつ、ほとんど万人に好まれる食品という条件を満たすものとして、サワードウ・スターターに決定した。
その決定には別な狙いも含まれているように思える。「自家製のサワー種で作るサワードウブレッドから、大量生産の柔らかな白パンに切り替わる過程で起きたことは、栄養面でも、風味の面でも、必ずしも進歩ではなかったことくらい、栄養士でなくてもわかる。パンをこのように大規模に工業生産する必要はないのに、ほとんどがそうやって生産されている。私たちは、日々の糧とするパンのもつ独特の食感や、奥深い味と香り、豊かな栄養、そして、その元になる多様な微生物を失ってしまったのだ」。つまり、サワードウ・スターターを通して、微生物の多様性を見直そうとしている。
サワードウ・スターター研究は二部からなる。第一部(実験の部)では、14か国15人のパン職人それぞれに、同じ材料を使って同じスターターをつくってもらう。唯一コントロールされていない要素は、パン職人の身体と家屋および製パン所の空気で、それらがスターター中の微生物に影響を及ぼす、という仮説を検証する。研究の第二部(調査の部)は、スターターのグローバルサーベイで、世界中から集めたスターター中の微生物群の構成などを調べる。
グローバルサーベイの参加者たちが世界の各地からサンプルを送ってきたスターターの多くは、数百年前にまでさかのぼるとされる歴史をもっており、ほとんどのスターターには名前が付けられていた。そんな参加者たちはさまざまな疑問を抱いていた。「スターターは時間が経つにつれて変化していくのだろうか? 自分のスターターには、100年前に含まれていたのと同じ種類の微生物が含まれているのだろうか? スターターを保管する温度によって、何か違いが生じるのだろうか? どうすれば、酸味の強いパンや、酸味を抑えたパンになるスターターを起こせるのか? そのような諸々のことを知りたがっていた」
そんな疑問が提起されたところで、もう一冊の本、『発酵種(サワードウ)とパン~科学から応用まで~』にも注目してみたい。そこには、スターターへの餌やりの影響が、スターターに含まれる酵母と乳酸菌の視点から説明されている。
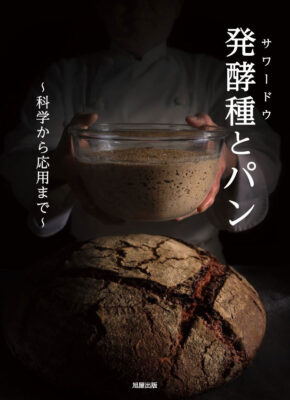
「植え継いでいく種には様々な変化が推測できます。
まずは、酵母の視点から。
市販されている酵母は増殖が速い酵母が選ばれていますので、もし、あなたのパン工房ですでに市販のパン酵母を使用しているなら、その酵母が自家培養発酵種に混入した場合、種継ぎを重ねていく中で、その酵母に置きかわるということが起こります。
一方、乳酸菌の視点から。
作った自家培養発酵種には、最初は多種類の乳酸菌がいたとしても、種継していくうちに、数種類の乳酸菌に淘汰されていきます。これは、乳酸菌も種類によって増殖速度が異なるため、速度が遅い乳酸菌は十分増殖することができず、植え継いでいくうちにどんどん菌数を減らし、最後にはいなくなってしまうということです。発酵種という環境の中で、乳酸菌も生存競争を繰り広げているわけです」
ロブ・ダンも、この「酵母の視点」に関心を持ち、本書でより詳しく説明している。まず、ある酵母の発見がいかにパン製造を変えたかについて。「デンマークの真菌学者、エミール・クリスチャン・ハンセンが、ビールの醸造に不可欠な微生物は、サッカロマイセス属の真菌であることを突きとめた。その後、このサッカロマイセス・セレビシエを加えただけで、新しいタイプのパン――酸味が全くなく、細菌の作用を全く受けずに、それでも膨らむパン――が作れることが明らかになった。科学者たちは、サッカロマイセス・セレビシエという単一の酵母を実験室で大量に純粋培養し、それをフリーズドライして世界中に送る方法を考え出した。このフリーズドライ酵母の出現によって、パン製造の大規模化が可能になった。今日、市販されているパンのほとんどは、わずかな種類の小麦のどれかと、大量培養されてパン製造会社に販売される単一品種の酵母を用いて作られている。この酵母は、さまざまな名前で呼ばれているので、まるでいくつもの種類があると思ってしまうが、そうではないのだ」
そのサッカロマイセス・セレビシエが、サワードウ・スターターにどう関わるのか。ロブ・ダンは、「小麦粉に水を加えて混ぜ合わせたのち、放置して待つ」というスターター作りに、以下のような注をつけている。「そうしている限り、サッカロマイセス・セレビシエがスターターの微生物群に加わることはめったにないようだ。ところが製パン所でパッケージ入りの酵母を使うようになると、すぐにそれが製パン所の屋内酵母菌群に加わって(攪拌機、小麦粉、保存容器などに広がり)、たちまち新たなスターターを「汚染」してしまうようだ。だからと言ってスターターの仕事が妨げられるわけではないが、スターターの多様性は乏しくなる。工業的規模でのサッカロマイセスの生産および利用によって起こる微生物の均一化を、さらに進めてしまう要因となるのだ」
ロブ・ダンのこのサワードウ・スターター研究プロジェクトは、本書の執筆中に開始されたもののようで、研究の結果が出そろい、まとめられているわけではない。それでも興味深い解析結果が紹介されている。
まずはその前提となる手を覆う微生物叢について。「それまでの研究から、どんな人の手も(手だけではなく、鼻、臍、肺、腸、および体表面すべてが)微生物叢で覆われていることがわかっていた。手を洗えば、そうした微生物がすべて除去されるように思いがちだが、そうはならない。誰かの手の微生物を採取したあと、手をごしごし洗ってもらい、それから再び微生物を採取しても、微生物の全体構成には何の変化も起こらない」。では、手洗いにどんな効果があるかといえば、手が無菌状態になるわけではなく、除去されるのは、手にくっついたばかりで、まだ定着していない微生物だけらしい。
そんな微生物叢を踏まえて、パン職人の手指に棲みついている微生物の解析結果はどうだったのか。サワー種を起こすのに役立っているのではないかとロブ・ダンたちが考えたのは、ラクトバチルス属細菌とその類縁種だが、通常は、ラクトバチルス属の細菌が手指から検出されるのは比較的珍しく、男性の手指から見つかる微生物のおよそ2パーセント、女性の場合はおよそ6パーセントでしかない。
「まず最初に驚いたのは、パン職人たちの手は、それまでに私たちが見てきたどの手とも全く違っているということだった。パン職人の手指に棲みついている全細菌のうち、平均で25パーセント、最高で80パーセントが、ラクトバチルス属細菌とその類縁種だった。同様に、パン職人の手指の真菌のほぼすべてが、サッカロマイセス属の真菌のような、サワー種の中に見つかる酵母だった。全く予想していなかったことで、その理由はまだ十分に解明できていない。これは私の推測にすぎないが、いつも触れている細菌や真菌が手指に定着するのではないだろうか」
では、パン職人とその職人が作ったスターターとの関係は? 「各スターター中の細菌が、そのスターターを作ったパン職人の手指の細菌と一致する確率は、それ以外のパン職人の手指の細菌と一致する確率よりも高かった」
さらに、あるパン職人の場合は、もっと深いつながりが明らかになった。「今回のパン職人たちの一人は、スターターの中に比較的珍しい真菌、ウィッカーハモマイセス属の酵母がいることでちょっと知られていた。今回の実験で、そのパン職人が起こしたスターターから、ウィッカーハモマイセス属の酵母が検出され、彼の手からもそれが検出された。この真菌が見つかったスターターは、彼のスターターだけで、この真菌が見つかった手は、彼の手だけであった」
筆者がサワードウ・スターターを起こすときにすんなりとはいかないのは、自分の手指を覆う微生物叢、あるいは家屋の空気などが関係しているのだろうか、とても気になる。
《参照/引用文献》
● 『家は生態系 あなたは20万種の生き物と暮らしている』ロブ・ダン著、今西康子訳(白揚社、2021年)
● 『発酵種(サワードウ)とパン~科学から応用まで~』「発酵種とパン」編集委員会著(旭屋出版、2023年)
《関連リンク》
● 「すごく久しぶりにサワードウ・スターターを起こし、手始めにチャバタをつくってみる」
● 「サワードウ・スターターを起こせた(ような気がした)ので、サワードウ・ブレッドを焼いてみて、失敗も含めた実験の楽しさを実感する」
[amazon.co.jpへ]
● 『家は生態系 あなたは20万種の生き物と暮らしている』ロブ・ダン著、今西康子訳(白揚社、2021年)
● 『発酵種(サワードウ)とパン~科学から応用まで~』「発酵種とパン」編集委員会著(旭屋出版、2023年)