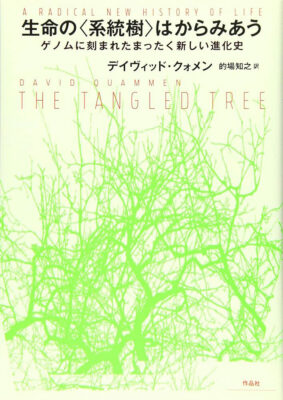2012年に『スピルオーバー――ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び移るのか』(邦訳は2021年)を発表したサイエンスライターのデビッド・クアメンが、その翌年に行った講演(TED Talks)は、新刊のプレゼンテーションになっているだけでなく、彼のキャリアの重要な分岐点に言及しているという意味でも非常に興味深い。
※『スピルオーバー――ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び移るのか』については、以前の記事「社会科学の視点でとらえたHIVから自然科学の視点でとらえたHIVへ――ランディ・シルツ著『そしてエイズは蔓延した』からデビッド・クアメン著『スピルオーバー』へ その1」で取り上げているので、内容についてはそちらを参照していただければと思う。
▼ デビッド・クアメンの2013年の講演「新しいパンデミックはすべてミステリー小説のように始まる」
この講演は、「12年前に、私の人生を変える言葉を耳にしました」という語りから始まる。その言葉とは「13頭のゴリラの死骸」だ。場所はアフリカ中部、ガボン北東部の森のなかで、クアメンはキャンプファイヤーを囲んでいた。そこにいた地元のふたりの男がエボラウイルスのことを話していた。そのキャンプ地から遠くない場所にある彼らの村で、エボラ出血熱のアウトブレイクが起こり、家族や村人たちが亡くなっていた。そんな話題のなかで出てきたのが、13頭のゴリラの死骸が山になっていたという話だった。
アウトブレイクの震源地で、それを体験した人間から13頭のゴリラの話を聞いたクアメンはすべてのことが身近に感じられた。そしてそこから、進化生物学と恐ろしいウイルスを理解するための長い探求の旅へと駆り立てられていった。その探求が彼を「安全地帯」から連れ出した。安全地帯とは、目に見える大きな動物について書くことだった。彼は人獣共通感染症を理解するために、見えないものを追求するようになった。
目に見える動物から見えないものへ。それはまさしく大きな分岐点であり、個人的にとても興味を覚えるのだが、この短い説明では、クアメンがそこでなにをしていたのかもわからず、状況が飲み込めない。13頭のゴリラが彼にどんな衝撃をもたらしたのかもはっきりしない。だからあまり印象に残らないかもしれない。
そこで、『スピルオーバー』の第Ⅱ章「13頭のゴリラ――エボラ」も参照しつつ、それがどんな分岐点であったのかを勝手に捕捉してみたい。ガボン北東部にある小さな村マイブート2で、エボラのアウトブレイクが発生したのは1996年2月初旬のことだった。その4年後の2000年、クアメンはガボン北東部の森にいた。その目的は、生物学者/環境保護活動家のマイク・フェイが主導する壮大で過酷なプロジェクトを取材することだった。
「『メガトランセクト』と名付けられたフェイのプロジェクトは、アフリカ中部の最も未開の森林地帯2000マイル(約3200キロ)を徒歩で巡る生物学的調査だった。彼は一歩進むごとにデータを取り、ゾウの糞の山やヒョウの足跡、チンパンジーなどの目撃情報、植物の同定情報など無数の記録を、右手に持った防水加工した黄色いノートに書きつけていった。後ろからはクルーたちがパソコン、衛星電話、特殊機器、予備用バッテリー、テント、食料、医療品などを持って付いて行った」
もちろん、クアメンがそのプロジェクトにずっと張りついていたというわけではない。「私の仕事は米誌『ナショナルジオグラフィック』のためにフェイの足跡をたどり、その研究ぶりと旅の様子を描くシリーズを執筆することで、こちらで10日間、あちらで2週間と彼らに同行してはアメリカへ逃げ帰り、足を治しながら(私たちはリバーサンダルを履いていた)一回分ずつ原稿を書いていた」
▼ クアメンがプロジェクト「メガトランセクト」の体験について語っている動画。
この動画によれば、フェイは456日かけて2000マイルを歩きとおし、クアメンは4つのセクションに分けて、トータル53日間、行動をともにしたという。そのセクションのなかに、エボラのアウトブレイクが発生した地域があった。その地域では、ゴリラが姿を消していたとも語っている。
クアメンがガボン北東部の森にいたのは、エボラと直接的に関わるプロジェクトのためではなかったし、エボラのアウトブレイクのことは知っていたものの、意図してその場所を選んだわけでもなかったようだ。だが、クルーとして雇われた現地の男たちから「13頭のゴリラ」の話を聞いたことで、進化生物学やウイルスを理解するための探求に駆り立てられていく。
しかし、クアメンを刺激したのはおそらく「13頭のゴリラ」の話だけではないだろう。それは4年前のことであって、彼自身がそれを見たわけではない。クアメンがアウトブレイクの4年後に現地を訪れ、フェイと行動をともにしたことで、見出したこともある。上の動画でも語っているように、ゴリラが姿を消していたことだ。『スピルオーバー』では、そのことが以下のように綴られている。
「この14日間の行程で、ゾウの糞の山は997個あったが、ゴリラの糞は一粒もなかった。何百万本もの草本植物が生い茂る中を通ってきて、その中には栄養価が高く、ゴリラがセロリのようにむさぼるクズウコン科の草もあったのに、彼が気付いた限りでは、ゴリラの歯型が残った茎は一本もなかった。ゴリラが胸を打つ音も聞かなければ、ゴリラの巣も見なかった。まるでシャーロック・ホームズに出てくる『夜中に犬に起こった奇妙な事件』のようだった。『犬が吠えない』ことは、何かが不自然であることの雄弁な反証だ。かつては豊富にいたミンケベのゴリラたちは姿を消していた。何かによって殲滅されたのではないかという推測を免れなかった」
クアメンは、地元の男たちから聞いた話だけでなく、自分の目でそこにいるはずのゴリラが姿を消したのを確認し、13頭のゴリラが特別な意味を持つようになり、重要な分岐点になったのだろう。さらに、この引用でもうひとつ見逃せないのが、彼が、ゴリラが姿を消したことを、ミステリー小説に例えていることだ。彼は、冒頭の講演(Ted Talks)でも、「新しい人獣共通感染症はどれもミステリー小説のように始まる」と語っている。さらに以下のクレアモント・マッケナ大学の講演の動画では、ミステリー小説についてもう少し長く語っている。
▼ デビッド・クアメンのクレアモント・マッケナ大学での講演(おそらく2016年頃)。
この講演では、エボラとHIVのふたつの物語が中心になる。その合間で、人獣共通感染症の原因になるウイルスの生物学的起源をめぐる謎を、ミステリー小説に例えている。彼は、もし楽しむという表現が許されるなら、人獣共通感染症に関する長い本を書くことが楽しかった、次から次へとミステリーの物語が展開していくからだと語り、さらには、陰惨な題材を、読者がページをめくりたくなるようなものに変えられるとも語っている。
クアメンがミステリー小説に言及するのは、場を和ませる狙いもあるだろうが、決してそれだけではない。たとえば、『スピルオーバー』のなかでHIVを扱った第Ⅷ章「チンパンジーと川――HIV」を読めばそれがわかる。クアメンは研究者たちと並走するようにエイズの起源に迫るだけでなく、まずエイズが蔓延した80年代アメリカで「患者ゼロ号」として注目されることになったガエタン・デュガのことに触れ、本当の「患者ゼロ号」を追い求めてアフリカへ、そして時間をさかのぼっていく。以前の記事「社会科学の視点でとらえたHIVから自然科学の視点でとらえたHIVへ――ランディ・シルツ著『そしてエイズは蔓延した』からデビッド・クアメン著『スピルオーバー』へ その1」でも触れたように、その構成はまさにミステリー小説のようでもあり、謎解きに引き込まれる。
ちなみに、この講演の最後でクアメンは参加者たちからの質問に答えているが、そのなかに興味深いやりとりがある。ある女性が、エボラ出血熱を引き起こすウイルスが生きているのかどうか、つまり、ウイルスが生物といえるのかどうかを尋ねる。
クアメンは質問に答えたあとで、このように付け足す。ウイルスが生きているかどうかよりも、もっと興味深い疑問は、彼らがどこから来たかのかということだと思います。彼らはどのように進化したのか。細胞よりも前に進化していたのか、細胞から切り離されたのか。さらに、次の本のプロジェクトのために、生命の起源やウイルスがどのように適応するのかを研究する科学者たちの論文を読んでいるとも語っている。
いまから振り返ると、その次の本のプロジェクトというのは、クアメンが2018年に発表した『生命の<系統樹>はからみあう ゲノムに刻まれたまったく新しい進化史』(邦訳は2020年、著者名の表記はデイヴィッド・クォメン)であることがわかる。
カール・ウーズによるアーキアの発見、遺伝子の水平伝播、リン・マーギュリスが世に知らしめた「細胞内共生説」という三つのサプライズを中心に生命の進化を見直す本書では、見えない生命の世界がさらに深く掘り下げられている。「13頭のゴリラ」という分岐点がなかったら、クアメンの方向性はまったく違ったものになっていたかもしれない。
クアメンにとって転換点となったのは2000年の出来事。パスカル・コサールの『これからの微生物学――マイクロバイオータからCRISPRへ』(邦訳2019年)のまえがきにある「21世紀は生物学の世紀になるだろうと言われた。それは間違いなく微生物学の世紀である」という記述が想起される。確かに21世紀は微生物学の世紀だと思う。
《参照/引用文献》
● 『スピルオーバー――ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び移るのか』デビッド・クアメン著、甘糟智子訳(明石書店、2021年)
● 『これからの微生物学――マイクロバイオータからCRISPRへ』パスカル・コサール、矢倉英隆訳(みすず書房、2019年)
[amazon.co.jpへ]
● 『スピルオーバー――ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び移るのか』デビッド・クアメン著、甘糟智子訳(明石書店、2021年)
● 『エボラの正体 死のウイルスの謎を追う』デビッド・クアメン著、山本光伸訳(日経BP、2015年)
● 『生命の<系統樹>はからみあう ゲノムに刻まれたまったく新しい進化史』デイヴィッド・クォメン著、的場知之訳(作品社、2020年)
● 『これからの微生物学――マイクロバイオータからCRISPRへ』パスカル・コサール、矢倉英隆訳(みすず書房、2019年)