ゲノム医療のパイオニアのひとりであるユアン・アンガス・アシュリーが書いた『ゲノム・オデッセイ』の内容は、「診断のつかない患者を救う、ある医師によるゲノム医療の記録」という副題が物語っている。心臓専門医であるアシュリーは、最も困難な症例の解決を目指す医師たちの全国的な未診断疾患ネットワークの最初の共同議長を務め、スタンフォード大学の未診断疾患センターで、確定診断を求めてさまよう患者たちと向き合い、ゲノム医療を通して病気の診断、治療に尽力してきた。
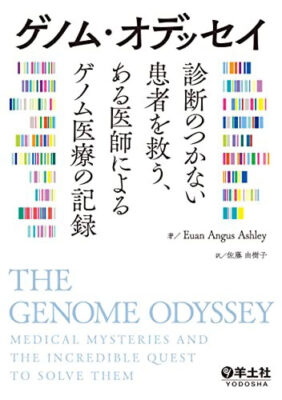
本書の第2部には「疾患探偵」というタイトルがつけられ、アシュリーはシャーロック・ホームズを引用して、ゲノム医療を探偵業にたとえている。そういうたとえは珍しいものではないが、彼のホームズの引用は念がいっている。ホームズの人物設定には、コナン・ドイルの医学的指導者のひとり、ジョセフ・ベル博士が大きな影響を与えたことを指摘し、以下のような記述がつづく。
「コナン・ドイルがこうした経歴の持ち主だったので、ホームズの物語の随所にさまざまな形で医学的な描写が用いられたのも不思議ではないだろう。第一作となった短編の冒頭でも、ワトソンがホームズに出会うのは病院の研究室だ。ホームズは、事件現場で血液を検出する能力を強化しようと、ヘモグロビンに反応する試薬を開発している最中だった。事実、シャーロック・ホームズの全話を通じて疾患に関する記述は68回、医者は38人、薬剤は22種類、医学の専門家は12人、そして医学雑誌は3種類登場する。
ホームズの犯罪捜査には、観察と広範な知識、人間性への理解が欠かせない。ホームズのこうした姿勢は、我々が医学的な謎に迫る手法と多くの点で共通する。ホームズはしばしば“見ること”(受動的行為)と“観察すること”(能動的行為)は違うと指摘する。『白銀号事件』で、ホームズは警部補が数分前に調べた現場の泥の中から、マッチの燃えさしを拾う。警部補は「なぜ自分はこんな大切なものを見落したのか」と言うのだが、これに対してホームズは「私はこれを探していたから見つけられたのだ」と答えている。同じように、我々は医学生に能動的に観察することを教える。徐脈が認められたら、大動脈弁の狭窄を示す心雑音がないかを確かめなければならない(後略)」
その後も、『緋色の研究』や『バスカヴィル家の犬』などを経て、ホームズの医学的要素が引き継がれたテレビドラマ『ドクター・ハウス』も取り上げ、そこに登場する診断チームの使命と、「アメリカ国立衛生研究所のビル・ガールが発案した、実在の未診断疾患ネットワークの使命とのあいだには、多くの共通点がある」と説明したうえで、このネットワーク発足の経緯が綴られていく。
未診断疾患ネットワークの扉が開かれたのは、公式には2015年9月16日。アシュリーにとっては、「内なるシャーロック・ホームズを目覚めさせる行為だった」。また、本書のタイトルは、診断のつかない疾患を抱えた人々を待ち受ける試練、孤独や苦しみと結びついている。「診断を求めてさまようこうした境遇は、いみじくも医療オデッセイと呼ばれている」からだ。
本書では、スタンフォード大学の未診断疾患センターに救いを求めた患者たちの症例が紹介されていくが、その前に第1部では、アシュリーにとって重要なターニングポイントとなった出来事、本書の出発点ともいえる出会いが取り上げられる。
それは2009年、アシュリーは未来の友人となるスタンフォード大学の物理学教授にして生物工学者のスティーヴ・クエイクのオフィスを訪れた。ふたりは遺伝学部のアフタヌーンシンポジウムを企画するつもりだったが、そこでスティーヴから予想外のものを見せられる。コンピュータの画面に広がっていたのは、スティーヴのゲノムだった。
2009年当時、全ゲノム配列が解読された人は世界中でも片手で数えられるほどしかいなかった。いずれのプロジェクトも何百人という科学者が関与し、何千時間もかけ、控え目な事例でも100万ドルかかっていた。「そんな状況の中で2009年、スティーヴは自身の研究室で、自分で開発した技術を使い、博士研究員のノーマ・ネフと博士課程の学生ドミトリー・プシュカレフの手を借り、たった4万ドルで自身のゲノムを解読した。それも1週間で」
しかし話はそんな驚きだけでは終わらない。スティーヴは自分のDNAが標準ゲノム配列と異なる箇所をいくつか指摘し、心臓専門医であるアシュリーはその中に「心筋ミオシン結合タンパク質C」という自分がよく知る遺伝子を見つけた。「今ではこの遺伝子の変異が、遺伝性の心臓病である肥大型心筋症――心不全や突然死を引き起こす疾患――の最も一般的な原因であることがわかっている。スティーヴは、まさにこの遺伝子の変異を指差していた。彼の遺伝子に見られる変異が命取りになる可能性はあった」
その結果、スティーヴはアシュリーの患者になった。以前から遺伝性心血管疾患センターの構想を温めていたアシュリーは、チームをつくって、ヒトの全ゲノムを臨床的に解析するというアイディアを実行に移す決断をする。それが本書の出発点になった。
▼ ユアン・アンガス・アシュリーとスティーヴ・クエイクのインタビュー。クエイクが本書の出発点となった自身のゲノム解読について自分の言葉で語っている。
その後、アシュリーと彼のチームは、クエイクにつづいて、今度はバイオテクノロジー企業ソレクサ社のCEOだったジョン・ウェストの依頼を受けて、ジョンと彼の一家のゲノム解析を行い、ウェスト一家は「ウォール・ストリート・ジャーナル」紙でゲノムのパイオニアと称賛された。「(ジョンの娘)アンは、この後の数年間で、科学者を相手にたびたびプレゼンテーションを行った。彼女は、自身のゲノム分析やその結果についてオープンに語り、これらの成果はもはや自分の人生に欠かせないものになったのだと熱烈に語った。
▼ サウスウェスタン大学のシンポジウムで家族の全ゲノムシークエンシングについて語るアン・ウェスト。
アシュリーが未診断疾患ネットワークの共同議長を務めることになったのは、こうしたゲノム解析の実績が認められたからだった。
本書で紹介されるさまざまなゲノム医療で考えさせられるのは、謎が解明されて診断が下ることがどんな意味を持つのかということだ。たとえば、バートランドという男の子とグレースという女の子、それぞれの両親を苦しめてきた病気について、以下のような記述がある。
「国や大陸を越えてゲノム科学者の巨大なチームと家族たちが手を携え、数年間の時を費やし、ついに新たな疾患が定義され、謎が解明された。答えはNGLY1遺伝子だった。だがこれで終わりではなかった。問題は、次の一歩だった」
そこから浮かび上がってくるであろう疑問が、以下のような記述に表れている。
「ときには、知るだけで十分なのかと問われることもある。治療法がないのなら、手に負えない病気に名前を与える意味などあるのか、と」
バートランドの両親は、発育が遅れ、発作があり、涙が出ない息子を連れて小児科や発育の専門家、小児神経科などを訪ねたが、そのたびに致命的な病気の可能性を提示され、検査をすると結局どの診断も却下されることになったという。そんな苦しみからは解放される。
ただし先述したようにゲノム解析でも簡単に答えが出たわけではない。NGLY1遺伝子の欠損が原因だと考えられたが、もしそれで間違いなければバートランドの症例が世界初になり、同じ病気の患者がいない現状では、確証が得られなかった。そこで、バートランドの父親は、息子の症状をブログに載せ、やがてもうひとりの患者であるグレースと結びつき、診断が確定することになる。
また、治療法とは少し違う意味で興味深いエピソードがある。バートランドの父親は生化学を学習し、NGLY1欠損症の患者には、GlcNAc(N‐アセチルグルコサミン)が足りないのなら、それを補えないかと考え、検索してみるとアマゾンでサプリメントとして錠剤が買えることがわかった。そして投薬をはじめて3日目にしてバートランドは大粒の涙を流して泣くようになった。診断はそうした結果も招く。
さらに、MEPAN症候群の診断を下された世界で8番目、および9番目の患者になるカーソンとチェイスの兄弟にも似たエピソードがある。このMEPAN症候群の場合は、アルファリポ酸を補えば、壊れたMECR遺伝子が形成できなかった物質を供給したことになり、少年たちの遺伝的な問題を回避できる。そのアルファリポ酸はボトル1本当たり16ドル95セントも出せばアマゾンで購入できるという。
「カーソンとチェイスは、製造ラインの失われたパーツを補うために、アルファリポ酸と中鎖脂肪酸トリグリセリド(MCT)オイルの服用を開始した。驚くべきことに、数カ月後には効果が現れるようになった。診断前、兄弟の運動遅滞は徐々に進行していた。カーソンは2歳にして自力で座ることも、1、2歩踏み出すこともできなくなった。チェイスは最初のころは腹ばいで前進できたのだが、1歳ごろにはその能力も徐々に失われていった。サプリメントをはじめてからは、機能の後退ば横ばいになり、ふたりを担当する神経科医は改善すら認めた」
ここで、スティーヴ・クエイクが自身のゲノムを解読したときのことを振り返ってみたい。彼は自分のDNAが標準ゲノム配列と異なる箇所をいくつか指摘したが、この標準ゲノム配列とは何なのかが後に明らかにされる。
「細々したことをたくさん学ばなければならなかった。例えば、変異を検知するコンピューターコードは、標準ゲノム配列(ヒトゲノム計画でもたらされた配列)に含まれる変異は無視するようにプログラムされていた。標準ゲノム配列が本当の意味で健康な“標準”ゲノムであれば――すべての遺伝子の理想形であれば――これも頷ける。しかし、標準ゲノムは実在の被験者に由来するため、疾患に結びつく変異をかなり多く含んでいることがわかった。そこで、該当する配列については書き換える必要があった」
「あれこれ話し合った末に、博士課程を修了した新しい顔ぶれのリック・デューイから、素晴らしいアイディアが飛び出した。どんな遺伝性疾患であれ、ほとんどの人が持っていないと考えるのが妥当だ、と彼は言った。であるならば、標準ゲノムのひとつひとつの文字を他のゲノムと比較したときに、最も一般的でない文字を拾い出し、それを最も一般的な文字に置き換えればいいのではないか? そうすれば、事実上、病気を持たない標準ゲノムになる。そもそも標準を名乗るからには、他の医学的指標と同じく、“正常な”集団の最大派閥を代表するものであるべきではないか?」
この課題は、ヒトゲノム計画のリーダー、フランシス・コリンズのその後とも結びつく。2003年、ヒトゲノム計画が完了して間もなく、コリンズは理論派の人々を一堂に集めた。
「彼らは、ヒトゲノム計画の潜在的な力を具体化するには、数十万、あるいは数百万という人々の遺伝的多様性を明らかにすることが重要であると理解していた。大規模な集団を分析できて初めて、重要な意味を持つ遺伝的変異を――どの変異が疾患の原因となり、どの変異が無害であるのかを――あぶり出せるのだ」
そうしたビジョンは具体化されつつある。本書では、アイスランドやイギリス、アメリカにおけるプロジェクトに触れたあとで、以下のようにまとめられている。
「近いうちに、パソコンとインターネット環境さえあれば、世界中の研究者が数十億から数兆というデータポイントにアクセスできるようになる。世界中の何百万という人々の医療記録やゲノムデータの中から必要な見識を得られるようになるのだ。これらの見識こそが、ヒトの疾患の謎を明かし、新薬の標的を絞り込む手掛かりになる。とはいえこれは、大統領や首相、患者やプロジェクトの参加者、教授、それに純粋に好奇心を抱く人々の心を捉えてきたオーダーメイド医療という夢の実現へ向けた、第一歩に過ぎない。そして最も驚くべきは、オーダーメイド医療の時代を開く鍵が個々の理解ではなく、人類全般――オール・オブ・アス――の理解にあるということなのだろう」
ちなみに本書では、オーダーメイド医療の可能性を示す事例が紹介されている。患者は、バッテン病という不治の病の特殊な症例で苦しむ少女ミラ。ボストン小児病院の小児遺伝学・神経学者のティモシー・ユーは、彼女の全ゲノムを精査し、あるはずのないDNA、長さ2000塩基の“ジャンピング遺伝子”を見つけ、研究者たちに協力を求めて、ジャンピング遺伝子の働きを抑制するよう設計された薬剤を開発した。
「彼らはたった1年で、ゲノムシークエンシングからオーダーメイドの遺伝子治療を実現させた。ユーの成功は、頑固なまでの意志と、経験と勘を駆使して猛烈なスピードで進められた新薬開発がもたらした偉業だ。誰にでも当てはまる手法ではないし、当然のことながらコストも高くついた(家族が寄付金を募ってほぼ全額をまかなった)。ただ、真の意味でのオーダーメイド医療がもたらす可能性を示す、またとない事例となったのは間違いない」
《参照/引用文献》
● 『ゲノム・オデッセイ 診断のつかない患者を救う、ある医師によるゲノム医療の記録』ユアン・アンガス・アシュリー 佐藤由樹子訳(羊土社、2022年)
[amazon.co.jpへ]
● 『ゲノム・オデッセイ 診断のつかない患者を救う、ある医師によるゲノム医療の記録』ユアン・アンガス・アシュリー 佐藤由樹子訳(羊土社、2022年)