2015年頃から相次いで翻訳出版されたマーティン・J・ブレイザーの『失われてゆく、我々の内なる細菌』やアランナ・コリンの『あなたの体は9割が細菌――微生物の生態系が崩れはじめた』、エド・ヨンの『世界は細菌にあふれ、人は細菌によって生かされる』などには、共通するデータが取り上げられ、それぞれにヒトと微生物の関係が掘り下げられていく。

微生物学教授であるマーティン・J・ブレイザーの『失われてゆく、我々の内なる細菌』は2014年の著書で、2015年に翻訳が出た。「ピロリ菌の根絶は、利益よりも、より大きな健康被害を人類にもたらすかもしれない」という記述が示唆するように、ブレイザーは、ピロリ菌をヒントに、喘息、肥満、胃食道逆流症、若年性糖尿病、食物アレルギーなど、現代の疫病の謎に迫っていく。
そんな本書から冒頭で言及した共通するデータを抜き出すと、以下のようになる。
「ヒトの体は三〇兆個の細胞よりなる。一方、ヒトは、ヒトとともに進化してきた一〇〇兆個もの細菌や真菌の住処である」
「ヒトの体内細菌は数百万個の独自の遺伝子を持っているということである。より最近の推定によると、それは二〇〇万個という。一方、ヒト・ゲノムは二万三〇〇〇個の遺伝子を持つ。別の言葉に置き換えれば、私たちの身体内外に存在する遺伝子の九九パーセントが細菌由来で、残りの一パーセントがヒト由来ということになる」

進化生物学者であるアランナ・コリンの『あなたの体は9割が細菌』は2015年の著書で、2016年に翻訳が出た。彼女はマレーシアの野生生物保護区でコウモリの研究をしているときにダニに食われ、熱帯病に感染し、抗生物質を長期にわたって大量に投与することを余儀なくされた結果、体内の微生物がどれだけ重要な存在だったのかを意識するようになった。
この記事のタイトルは、「あなたの体はあなたのものである以上に、微生物のものでもあるのだ」という記述を参考にした。本書から、共通するデータを抜き出すと、以下のようになる。
「微生物は腸管内だけで100兆個存在し、海のサンゴ礁のように生態系をつくっている。およそ四〇〇〇種の微生物がそれぞれの小さなニッチを開拓し、長さ一・五メートルの大腸表面を覆う襞に隠れるようにして暮らしている。あなたは生まれた日から死ぬ日まで、アフリカゾウ五頭分の重量に匹敵する微生物の『宿主』となる。微生物はあなたの皮膚の上にもいる。あなたの指先には、イギリスの人口を上回る数の微生物が付着している」
「人体に棲むこれらの微生物を合わせると、遺伝子の総数は四四〇万個になる。これがマイクロバイオータのゲノム集合体、つまりマイクロバイオームである。微生物の四四〇万個の遺伝子は、二万一〇〇〇個のヒト遺伝子と協力しながら私たちの体を動かしている。遺伝子の数で比べれば、あなたのヒトの部分は〇・五%でしかない」

サイエンスライターのエド・ヨンの『世界は細菌にあふれ、人は細菌によって生かされる』は2016年の著作で、2017年に翻訳が出た。ヨンは、微生物研究の現状を客観的にとらえることに徹し、それが共通するデータの扱いにも表れている。
「平均的な人は、ヒト細胞の10倍の微生物細胞を持っているといわれているが、実際の体に当てはめると丸め誤差が出る。それにもかかわらず、大雑把な計算による10対1という割合が、書籍や雑誌、TEDトーク、これをテーマとする実質的にすべての科学記事で事実のように扱われている。だがこれはほとんど当てずっぽうの値といっていい。最新の推定値によると、われわれはおよそ30兆個のヒト細胞を持ち、39兆個の微生物細胞を持つという。つまり、およそ同数である。これらの数値は不正確だが、いずれにせよ、さして問題はないだろう。どう見ても、われわれは『無数のもの』を含むのには違いないのだから」
では、こうした共通するデータを踏まえて、ヒトと微生物のどのような関係が浮かび上がってくるのか。「失われてゆく、我々の内なる細菌」という邦題や、『あなたの体は9割が細菌』の副題「微生物の生態系が崩れはじめた」が示唆するように、抗生物質の多用や生活環境、食生活などの変化によって、体内の微生物の生態系が崩れ、あるいは失われ、それが現代の疫病の原因になっている可能性がある。しかし、そのことについては別の機会に触れることにしたい。
この共通するデータを踏まえて、微生物の世界をさらに掘り下げると、ヒトとの関係についてより根源的なテーマが浮かび上がってくる。

生物学者であるマーリン・シェルドレイクの『菌類が世界を救う――キノコ・カビ・酵母たちの驚異の能力』は2020年の著書で、2022年に翻訳が出た。「菌類の生活を理解しようとする試みの記録」である本書にも、以下のように共通するデータが提示されている。
「私たちの身体に棲みついた四十数兆個の微生物は、私たちが食物を消化するのを助け、重要なミネラルを生成する。植物の中で生きる菌類と同じく、これらの微生物は私たちを病気から守ってもくれる。私たちの身体と免疫系の発達をうながし、私たちの行動に影響を与える。きちんと抑制しなければ、病気をお起こし、死を招くことすらある」
しかし、その先には異なるテーマが浮かび上がってくる。
「とりわけ私たちが文化的に重要視してきたアイデンティティ、自律性、独立性の概念など、どれほど多くのアイデアを考慮し直すべきかを考えると目が回りそうだった。微生物学の発展をきわめて刺激的になものにするのは、まさにこうした混乱の感覚である。ヒトと微生物の関係は他の生物どうしの関係と変わらず親密そのものだ。だからこの関係についてより多くを学べば、私たちが自分の身体と環境をどう経験するかも変わってくる。『私たち』は境界を広げ、カテゴリーを超越する生態系なのだ。私たちの自己は、今ようやくその正体がわかりかけてきた複雑に絡みあった関係性から生まれるのである」

さらに、菌類学者ニコラス・マネーの2014年の著作で、2015年に翻訳が出た『生物界をつくった微生物』にも、同様の視点が提示されている。まずは共通するデータの記述から。
「我々人間は口から肛門までつながった消化管の中や、性器の湿った場所、命を支える呼吸器などに、微生物の大集団を詰めこんで運んでいる動く生態系なのだ。人間の皮膚は、面積が最も広い病原菌に対抗するバリアーだが、それは細菌や酵母でできた四番目の防御生態系に覆われている。我々のDNAの大部分がウイルス由来であるのと同時に、真核生物としての我々の細胞も微生物的要素から成り立っていると考えると、彼ら(微生物)と我々(受精卵から始まる細胞集団)の間の違いにこだわることが、ますますどうでもよくなってしまいそうである」
ここまでは共通するデータといっていいが、そこからテーマがより哲学的になる。
「デカルトは『我思うゆえに、我あり』と書き残し、地球上におけるほかの生命体と我々は、超自然的に区別されているという古来の信念を普及させた。四〇〇年経っても、まだ哲学の主流は人類の優越感に浸っている。ところが、最近になって生物学がひどく違ったことを言い始めた。それは、我々人間が培養された微生物の複雑な混合物以外の何物でもない(それ以上でも以下でもない存在)とする考えだが、もしそうなら、人間が『万物の霊長』だとする考えは、理屈に合わなくなるのである」
マネーはこの引用の数章前でもデカルトに言及し、「前世紀にルネ・デカルトはすべての生物を機械ととらえ、人間だけに不滅の魂が宿ると考えた」と書いている。
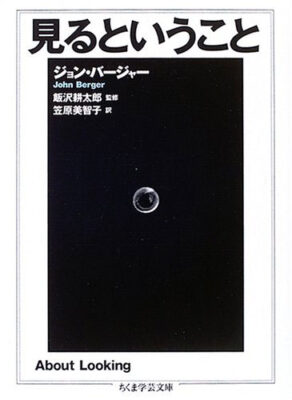
そこで筆者が思い出すのは、美術批評家ジョン・バージャーの『見るということ』に収められたエッセイ「なぜ動物を観るのか?」のことだ。バージャーが掘り下げているのは、ヒトと動物の関係の変化だが、ヒトと微生物の関係を考えるうえで非常に参考になる。
「二十世紀の企業資本主義によって完結をみる激動は、十九世紀の欧米に始まる。それによって人間と自然を繋いでいた伝統はすべて壊されてしまった。この崩壊が起こる以前に人間を取り巻く最初の輪を形成していたのは動物である。そのこと自体、そこに大きな違いがあることを示唆しているだろう。動物は人間と共に世界の中心に存在していた。このような中心性はもちろん経済的、生産的な意味においてである。生産手段や社会組織がどのように変わろうと、人間は衣食や労働、交通の面で動物に依存していた」
「なぜ動物を観るのか?」というタイトルは、以下のような記述に関わっている。
「動物が人間を見るとき、彼らの目は慇懃で油断なく見える。動物が他の動物を見るときも同じだろう。動物は人間だけを特別扱いしているわけではない。けれど人間以外、動物の視線を親しみをもって受け入れる種はない。他の動物はその視線によって押し止められる。人間はその視線を返すことによって自分自身を認識する」
そこから人間と動物の二元論について様々な考察を加え、分岐点としてデカルトに言及する。
「決定的な理論的分岐点はデカルトによってもたらされた。デカルトは人間と動物の関係に内在している二元論を人間の中に採り入れて自己のものとした。魂と肉体を完全に分け、肉体を物理学や力学の法則に依るものとした。魂がないのだから動物は機械の法則に還元される」
動物は下位に貶められ、テクノロジーの発展によって周縁へと追いやられていく。その代わりに人間はペットを飼い、動物園が造られていく。しかし、人間とペットの関係では両者の自立性が失われ、それぞれの生活の並行性は崩れる。動物園ではもはや人間と動物が視線を交わすことはなく、出会いは成立しない。
「動物の周縁化の最終結果がここにある。人間社会の発達に決定的な役割を果たし、一世紀弱前まで、常にすべての人間が共に生きた、動物と人間との間に交わされた視線が失われつつある。動物を見ている来園者、視線を相手から返されることのない人間は孤独である。それは最終的に群れとして孤立していく種なのだろう」
このエッセイが発表されたのは1977年のことで、微生物の存在は現在のようには認知されていなかった。ヒトと微生物は当然のことながらお互いに視線を交わすことはないが、その共生関係には、自立性があり、並行性があり、かつてヒトと動物の関係に内在していた二元論が成り立つようにも思えてくる。そんな二元論を想定してみると、「人間は孤独」ともいえなくなる。
《参照/引用文献》
● 『失われてゆく、我々の内なる細菌』マーティン・J・ブレイザー 片岡夏実訳(築地書館、2018年)
● 『あなたの体は9割が細菌――微生物の生態系が崩れはじめた』アランナ・コリン 矢野真千子訳(河出書房新社、2016)
● 『世界は細菌にあふれ、人は細菌によって生かされる』エド・ヨン 安部恵子訳(柏書房、2017年)
● 『菌類が世界を救う――キノコ・カビ・酵母たちの驚異の能力』マーリン・シェルドレイク 鍛原多恵子訳(河出書房新社、2022年)
● 『生物界をつくった微生物』ニコラス・マネー 小川真訳(築地書館、2015年)
● 『見るということ』ジョン・バージャー 笠原美智子訳(ちくま学芸文庫、2005年)