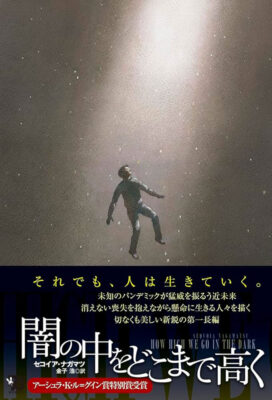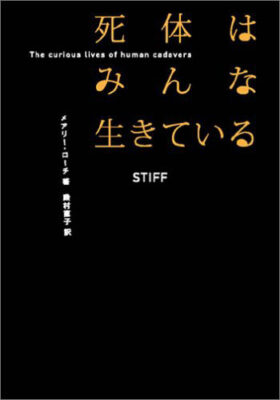(「セコイア・ナガマツが『闇の中をどこまで高く』で切り拓いた独自の世界とそのヒントになった、死に関する数冊のノンフィクション その1:葬儀業界と臨死体験」)からのつづき。
「その1」と重複するが、まずは『闇の中をどこまで高く』の巻末の謝辞にある以下の記述を再度、確認しておきたい。
「また、以下に挙げる著作も、死と悲しみという複雑な対象を分析するにあたって、そしてしばしば、わたし自身の喪失を乗り越えるためにおおいに役に立った。シャーウィン・B・ヌーランドの『人間らしい死にかた 人生の最終章を考える』とHow We Live(未訳)、ジェシカ・ミットフォードのThe American Way of Death(未訳)、メアリー・ローチの『死体はみんな生きている』、ピム・ヴァン・ロンメルのConsciousness Behind Life(未訳)」
ナガマツが独自の世界を切り拓くうえで、こうした死に関するノンフィクションがどのようなヒントをもたらしているのかに興味を持ち、探っている。「その1」では、遺族の悲しみにつけ込んで暴利をむさぼるような、葬儀業界の実態を明らかにするジェシカ・ミットフォードの『The American Way of Death』が、子供たちに安らかな最期を迎えさせる安楽死パークを舞台にした2番目の章「笑いの街」や遺族が死者との別れの時間を過ごす施設を舞台にした5番目の「エレジーホテル」に結びつき、多くの症例をもとに臨死体験を科学的に検証するオランダの心臓専門医ピム・ヴァン・ロンメルの『Consciousness Behind Life』が、語り手が場所も定かでない闇に包まれた空間で目覚める3番目の「記憶の庭を通って」に結びつくと勝手に想像した。
ここではまず、メアリー・ローチの『死体はみんな生きている』に注目したい。この本では、死体がわたしたちが知らないところで、外科の技術の発展のために切り刻まれたり、自動車事故の実験台になったりして、さまざまなかたちでいかに貢献してきたのかが描かれる。
そのなかの第3章「死後の生~人間の腐敗と防腐処理」の冒頭では、ある施設のことが以下のように説明されている。「この心地よいノックスヴィルの丘陵地に、世界中でただ一つの、人体の腐敗を研究する施設がある。ここに寝ている人々は死んでいる。彼らは献体された死体で、黙ってにおいを発散させながら、犯罪科学捜査の進歩に役立っている。死体がどのように腐敗していくのかを詳しく知れば知るほど、死体の死亡時刻の推定が容易になる。つまり、腐敗は一定の生物学的化学変化の段階をたどるので、それぞれの段階がどれぐらい持続し、環境にどのように影響されるかを調べるのだ。警察は殺されて間もない死体について、かなり正確な死亡時刻を言い当てることができる。(中略)
死後三日以上経つと、捜査は昆虫学的手がかり(つまり、ハエの幼虫がどれぐらい成長しているか)と、腐敗の段階に目をとめる。その腐敗の進行は、気象や置き場所などの環境によって異なる。天気はどうだったか、死体は埋められていたか。その場合はどこに埋められていたか。これらの要素の影響をもっとよく知るために、テネシー大学(UT)の法医人類学会(と、ぼかして呼ばれている)は、死体を浅い墓に埋めたり、コンクリートに閉じ込めたり、車のトランクに入れて人工池に沈めたり、ビニール袋に入れたりしている。つまり、殺人者が死体を処分するためにしそうなほとんどすべてのことを、UTの研究者は行っている」
そんな施設の記述と結びつくのが、7番目の章「腐敗の歌」だ。語り手であるわたし(名前はオーブリー)は、法医学死体農場に勤務する医師。これまで殺人事件の捜査に協力してきたが、パンデミック以後は北極病の研究にも協力するようになった。彼女は、北極病がどのように人体を変容させ、脳に肝組織を、腸に心臓組織を生じさせるのかを研究している。「ほとんどの死体は、エレジーホテルに宿泊していた家族が研究のために献体してくれたもので匿名だ」とあるように、5番目の章ともつながっている。この物語では、死体の試験場が以下のように描かれている(そこに登場するオーリーという人物については後述する)。
「翌日、わたしはオーリーと並んで上部が有刺鉄線になっているフェンスの前に立っている。反対側では十体以上の死体が待っている――コヨーテの餌にならないようにするためのゲージのなかで横たわっている死体もあれば、飢えた野生動物に食い荒らされてばらばらになっている死体もある。人工池の底では若い女性がじっとしている。その女性は足首に重りをつけられ、祈りに没入しているかのように両手を高々と上げている。水は濁っていて、オーリーにその女性の体は見えない。わたしがアリスという愛称をつけたその女性は、ここで法医学を学んでいる学生たちが水中での腐敗の速さを調べられるように、あとひと月は水中にとどまる。すべての死体が感染症の犠牲者というわけではない。わたしたちはいまも警察に協力している。だがアリスは、第二波初期の成人犠牲者のひとりだ。わたしは、池のなかでウイルスが、スノードームの雪のようにアリスのまわりに漂っているさまを思い描く。オーリーは鼻をおおう。ここでは、悪臭が毛穴にまで食いこんでくる。二度、三度とシャワーを浴びなければならない。いつまでたっても慣れない臭いだ」
あと、これは結びつきとまではいえないが、いくらか参考にはなるかと思うので、4番目の章「豚息子」とこの『死体はみんな生きている』の関連性についても書いておきたい。この章の語り手は、臓器移植によって感染者を救うため、心臓などの臓器を豚の体内で育てるプロジェクトを進める研究医だが、遺伝子組み換えを施されたドナー豚の一匹であるスノートリアスが、言葉を喋るようになり、脳が急速に発達していく。
この章では、研究医と豚のスノートリアスの関係が描かれるが、『死体はみんな生きている』でも、まったく違うかたちで、人間と豚の関係に短く言及されている。アメリカとヨーロッパの弾創研究で銃口を向けられたのは、ほとんどの場合は豚だったという。「ブタが撃たれるのは、汚くて気持ちが悪いとさげすむ文化のせいではない。ブタと人間の臓器に共通点が多いからだ。ブタの心臓は特に人間とよく似ている」。
ナガマツは、謝辞に挙げたノンフィクションをヒントに、死と深く関わるさまざまな状況を生みだす。それぞれの章の語り手は、パンデミックのなかで、これまでにない他者との関係を築くと同時に、過去を振り返り、今後について逡巡することになる。だが、パンデミックがその時間を削りとり、選択肢はなくなり、できることをやるしかなくなる。それが死を受け入れることにもつながる。
2番目の「笑いの街」の語り手スキップは、安楽死パークで行われている治験に参加するためにやってきたドリーとフィッチという母子と疑似家族的な関係を築く。スキップが母子にのめり込むのは、彼が以前に弟を亡くし、その喪失をめぐって両親とのあいだにわだかまりがあることと無関係ではない。母子と自分の両親の狭間で揺れながら、彼にできることは限られていく。
臨死体験がヒントになっていると筆者が想像する3番目の「記憶の庭を通って」では、場所も定かではない闇のなかで目覚めた語り手が、同じように混乱している人々に出会うが、特に印象に残るのは、彼らが泣いている赤ん坊を見つけたときのやりとりだ。彼らは口を揃えて、この子にはチャンスさえなかったと言う。彼らには少なくともそこに至るまでに選択肢があった。だから、彼らにできることをして、赤ん坊にチャンスを与えようとする。
先述した4番目の「豚息子」の語り手は、2番目の「笑いの街」に登場するフィッチの父親、ドリーと別れた夫であり、ドリーは今も彼が息子の最期の瞬間に立ち会わなかったことを責めている。「豚息子」というタイトルが示唆するように、彼は知性を持った豚スノートリアスを息子に重ね、その運命と向き合い、できることをしようとする。
5番目の「エレジーホテル」では、死別コーディネーターとして働く語り手デニスが、同じような経験をしている同僚に説得されるものの、母親が癌で死につつあるという現実から逃げつづけ、ある意味で逃れようのない場所に行き着くことになる。
そうした流れを踏まえると、先述した『死体はみんな生きている』がヒントになっていると思われる7番目の「腐敗の歌」の物語がより興味深く思えてくる。法医学死体農場に勤務する語り手オーブリーは、レアードという人物と新たな関係を築く。死体農場にある死体は、エレジーホテルに宿泊していた家族が研究のために献体してくれたものだが、レアードは特例で、みずから志願し、まだ生きている。彼は、「化学の学士号を持っていて副専攻で音楽を学んだだけにもかかわらず、ほかのだれかが解決策を見いだすのを手伝いたがった」。これまでに豚の臓器移植を三度受け、五度の治験を生きのびている。
オーブリーには、救急救命士として働くタツという夫がいる。レアードには、彼の面倒をみるオーリーという姉がいる。それが、先ほどの死体の試験場を描いた引用に出てきたオーリーだ。だが、オーブリーとレアードは、音楽の趣味でも共鳴し、家族とは異質で、より親密な関係を築いていく。レアードが亡くなったあとまでも。
レアードの死体は法医学死体農場のラボが保管し、試験場に移される。オーブリーは、彼の死体が腐敗していくのも見届けるが、死体がたどる運命については、『死体はみんな生きている』の現実が反映されているように思う。ここで思い出したいのは、先ほどの引用のなかの「つまり、殺人者が死体を処分するためにしそうなほとんどすべてのことを、UTの研究者は行っている」という記述だ。レアードの死体は、オーブリーが疾病対策センター(CDC)のために行っている研究に役立てられるだけでなく、犯罪捜査の訓練のためにも活用される。
死体は、Tシャツにジーンズ、靴下という服装で、浅い墓に2週間以上埋められたあと、ほかの墓に移される。その作業は、あらかじめ作成された犯罪のシナリオに基づいていて、法医学専攻の院生や地元当局関係者の混成集団が、行方不明者捜索の訓練を行う。死体捜索犬を使って死体を発見した院生たちは、死体が動かされたこと、第二の墓で見つけた若齢幼虫が死亡推定時刻を割りだすために使えないことを見抜かなければならない。そして、体内や周囲の土壌組成、細菌や微生物を手がかりに状況を把握していく。
やがて死体は、空で輪を描くコンドルや、フェンスのどこかに空いた穴をくぐり抜けるコヨーテに荒らされ、試験場でばらばらになる。院生や地元当局関係者にとって、それは死体のひとつに過ぎず、オーブリーだけがその正体を知っている。
この章がなぜ印象に残るのか。本作は、シベリアの永久凍土から三万年前の少女の死体が発見される章からはじまり、新天地を求めて宇宙に飛び出した人々が、地球から582光年、飛行期間6000年の彼方に到達するが、一方で、ある語り手を通して人類が誕生する以前へと時間をさかのぼり、三万年前の少女の正体も明らかにされる。その語り手だけがそれを知っている。
この符号はもしかすると偶然ではないかもしれない。ナガマツのインタビューによれば(たとえば、「Sequoia Nagamatsu on Writing the Grief and Connections of an Enduring Pandemic by Jane Ciabattari | Literary Hub」)、本作はもともとそれぞれに独立した物語が、次第につながるようになったもので、最初の章は実際には最後に書いたものであるという。そうなると、巻末の謝辞に挙げられた死や死体に関するノンフィクションを踏まえて、ナガマツが切り拓いた独自の世界について考えてみるのも意味があるように思える。
《参照/引用文献》
● 『闇の中をどこまで高く』セコイア・ナガマツ、金子浩訳(東京創元社、2024年)
● 『人間らしい死にかた――人生の最終章を考える』シャーウィン・B・ヌーランド、鈴木主税訳(河出書房新社、1995年)
● 『How We Live』Sherwin B.Nuland (Knopf Doubleday Publishing Group, 1998)
● 『死体はみんな生きている』メアリー・ローチ、殿村直子訳(日本放送出版協会、2005年)
● 『The American Way of Death Revisited』Jessica Mitford (Vintage; Reprint版, 2000)
● 『Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experience』Pim van Lommel (HarperOne; Reprint版, 2011)
[amazon.co.jpへ]
● 『闇の中をどこまで高く』セコイア・ナガマツ、金子浩訳(東京創元社、2024年)
● 『人間らしい死にかた――人生の最終章を考える』シャーウィン・B・ヌーランド、鈴木主税訳(河出書房新社、1995年)
● 『How We Live』Sherwin B.Nuland (Knopf Doubleday Publishing Group, 1998)
● 『死体はみんな生きている』メアリー・ローチ、殿村直子訳(日本放送出版協会、2005年)
● 『The American Way of Death Revisited』Jessica Mitford (Vintage; Reprint版, 2000)
● 『Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experience』Pim van Lommel (HarperOne; Reprint版, 2011)