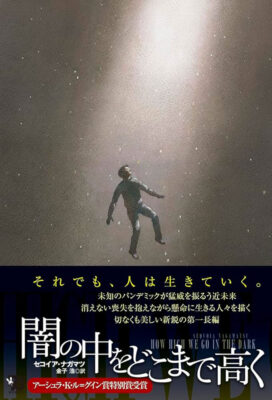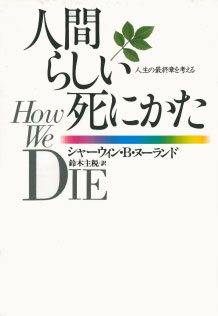日系アメリカ人のセコイア・ナガマツが2022年に発表した長編デビュー作『闇の中をどこまで高く』は、2030年のシベリア、気候変動を研究するチームが、解けつつある永久凍土のなかから三万年前の少女の死体を発見するところからはじまる。研究チームは、その少女の体内から見つかったウイルスに感染し、その後、「北極病」と呼ばれるようになる感染症が世界中に拡大していく。
そのウイルスは、特に子供や弱者に感染し、宿主細胞にほかの機能を果たすように命じ、肺の細胞と組織が肝臓のようになり、心臓は小さな脳の構造に変化する。この物語では、短篇を連ねたように章ごとに語り手が変わり、パンデミックの世界が多面的、重層的に描き出されていく。前半はほとんど2030年代を中心に展開するが、科学者や軍人を中心とした人々が新天地を求めて恒星間宇宙船で宇宙に旅立つことで、最終的に地球から582光年、飛行期間6000年の彼方に到達する一方、終盤には時間を一気にさかのぼり、人類が誕生する以前から地球の歴史が語りなおされる。
地球温暖化によってシベリアの永久凍土が解けだすことからすべてがはじまり、カリフォルニアは毎年のように山火事に見舞われ、2100年代の日本の新潟が海面上昇によって列島になっているなど、本作はクライファイ(気候変動フィクション)として読むことができるし、壮大なスケールのSFでもあるが、著者のブレのない視点と物語が醸し出す独特の空気を踏まえるならやはり、死を扱うスペキュレイティブ・フィクションというべきだろう。
それに関して見逃せないのが巻末の謝辞だ。カール・セーガンのテレビドキュメンタリーシリーズ<コスモス>や『スター・トレック』の影響に言及したあとに、以下のような記述がつづく。「また、以下に挙げる著作も、死と悲しみという複雑な対象を分析するにあたって、そしてしばしば、わたし自身の喪失を乗り越えるためにおおいに役に立った。シャーウィン・B・ヌーランドの『人間らしい死にかた 人生の最終章を考える』とHow We Live(未訳)、ジェシカ・ミットフォードのThe American Way of Death(未訳)、メアリー・ローチの『死体はみんな生きている』、ピム・ヴァン・ロンメルのConsciousness Behind Life(未訳)」
このなかで筆者が知っていたのは、邦訳がある2冊だけだったが、それでもこのリストが小説の内容と密接に結びついていることは容易に察することができる。イェール大学の外科・医学史教授だったヌーランドは『人間らしい死にかた』の趣旨を以下のように説明している。
「この本を書いた目的は、死という過程にまつわる神話を取り除くことである。だからといって死を、苦痛にさいなまれ人間性が失われていく恐怖にみちた過程として描くつもりは毛頭なく、その現実を自分の目で見た人が見たとおりに、そして臨死体験をした人が感じたとおりに、生物学的ならびに臨床的な事実として描いてみたいと思う。人の死にゆくさまを素直に語りあってはじめて、われわれが最も恐れている死の側面に対処できる。真実を知り、その心構えをすることによって、死という未知の世界への恐怖を免れ、自己欺瞞や幻滅を免れることができるのである。
死や臨終を描いた文献は数えきれないほどある。そのほとんどすべてが、死の過程と死後にともなう残された者の心の痛手を克服する手助けをしようとの意図に発するものだ。肉体が滅びていく詳細については、たいていの場合、あまり強調されていない。さまざまな疾病が人間の活力を吐き出させ、生命を奪いとっていく実際の過程については、専門誌に描かれるだけである」
これに対して、メアリー・ローチの『死体はみんな生きている』は、視点がまったく異なる。「本書は死について書かれた本ではない。臨終としての死は、悲しく深刻だ。愛する人を失ったときや自分自身が死のうとしているときに、おもしろいことは何もない。私が書こうとするのは、すでに死体となった、知らない人の死の舞台裏だ」。
本書では、外科の技術が発展するために切り刻まれたり、自動車事故の実験台になったり、美術展示品になったり、植物に取り込まれるなど、これまでわたしたちが知らないところで死体がいかに貢献してきたのかが描かれる(本書については、その2の記事でもっと引用する)。
そうなると、他の本がどんな切り口なのか知りたくなる。調べてみると、ジェシカ・ミットフォードの『The American Way of Death』では、遺族の悲しみにつけ込んで暴利をむさぼるような、葬儀業界の実態が明らかにされ、オランダの心臓専門医ピム・ヴァン・ロンメルの『Consciousness Behind Life』では、多くの症例をもとに臨死体験が科学的に検証されていることがわかった。
死に関わるとはいっても、「葬儀業界」と「臨死体験」は次元がまったく違う。そんなノンフィクションを謝辞で並置していることと、ナガマツが本作で切り拓く独自の世界は決して無関係ではない。簡単にいえば、そんな次元が違うエピソードが隣り合っている。
ここで比較してみたいのは、2番目の章(本作には目次がなく、数字を振ってないのでこういう表現になる)の「笑いの街」や5番目の「エレジーホテル」と、それらにはさまれた3番目の「記憶に庭を通って」の世界だ。
最初の章「三万年前からの弔辞」で、研究チームがウイルスに感染したあと、それにつづく「笑いの街」ではどんな物語が展開するのか。その舞台はカリフォルニアで新たに開業する「安楽死パーク」だ。北極病はアメリカにも上陸し、子供と弱者に感染が広がっている。そこで州知事が、「子供たちに安らかな最期を迎えさせるアミューズメントパークの計画を発表」するが、批判が巻き起こった。結局、息子を亡くしたドットコムタイプの億万長者が金を出して、刑務所の跡地に安楽死パークを試作させた。
この章の語り手は、仕方なくそこで働くようになる売れないコメディアの若者スキップ。仕事は、着ぐるみでパーク内を歩き回り、家族を楽しませ、子供たちが乗り物に乗るのを手伝うこと。感染した子供たちは、最後にジェットコースターに乗って息を引き取る。園長によれば、パークに来た子供は、親が考えを変えても、連れ帰ることは阻止しなければならない。安楽死パークは、政府と疾病対策センター(CDC)と契約を結んでいて、事業を継続するためには、ウイルス陽性者を施設外に出すわけにはいかないという。あくまで見せかけらしいが、元刑務所だったパークでは、高い監視塔から警備員がライフルで狙っている。
5番目の章「エレジーホテル」は、冒頭の文章が、物語の舞台と語り手であるデニスの仕事を簡潔に物語っている。
「哀歌(エレジー)ホテル最上階のワンルームのアパートメントには、おれのような死別(ビリーブメント)コーディネーターが住みこんでいる。同業者のなかには、自分は世界を救っているなどというおめでたい考えをいだいている連中もいるが、実際のところ、おれたちは、火葬を待つおびただしい数の北極病犠牲者のための、愛する家族の遺体の隣のスイートで丸まって眠り、傷を癒やすことを望んでいる家族のための、ていのいいベルボーイにすぎない。来る日も来る日も、地元の病院からバイオハザードバッグに詰められて運ばれてきて、三段階の保存プロセス、つまり殺菌とエンバーミングと抗菌プラスチック化処理を受けるのを待っている遺体が地下ホールに並んでいる。そのおかげで、家族は、火葬場が必死になって需要に応えているあいだにじっくりと別れを告げられる。仕事はちっとも難しくないし、贅沢を言わなければ給料も悪くない。エレジーホテルが誕生して葬儀市場を席巻して以来、おれは三年近く、過去についてはほとんど語らず、カリフォルニアのキングベッドから火葬炉へと死体を運んで、ひっそりと暮らしていた」
「笑いの街」のスキップと「エレジーホテル」のデニスは、パンデミックから生まれた仕事に就いている。彼らの仕事がパンデミックの一面を物語ることにもなる。これに対して、ふたつの章にはさまれた3番目の「記憶の庭を通って」の世界は次元が異なる。
語り手のぼくは、安楽死したいとこの告別式に出席し、子供たちのベビーシッターをしたことが原因で感染し、病院の感染症棟で目覚める。ところが、彼が隔離観察室にいる両親と話をしているうちに、体調が急変し、場所もさだかではない空間で目覚める。
「目が覚めると真っ暗だ。目をあけているのか閉じているのかもわからない。ぼくは助けを求めて叫ぶ。看護師に電灯をつけてほしい、そばにほかの患者がいるなら音をたててぼくがひとりじゃないことを教えてほしいと。着ているのは患者服ではなく、Tシャツとジーンズのようだ。鼻に呼吸チューブを挿入されていないし、痛みをやわらげるための点滴も受けていない。素足で踏んでいる帯電した空気の感触は、子供が思い描く雲にそっくりだ――乗っていられるほどしっかりしていて、なおかつその上を移動できる。まるで、無限に広がっている繭のようだ。引力が弱くなるのか、手を上げると指先が軽く感じられるが、だとすると体をここにとどめているなんらかの力が存在することになる。闇のなか、足の下を探っても、なんで立っていられるのかわからない」
この章には、臨死体験を示唆する表現は見当たらないが、臨死体験がヒントになっているのは間違いないだろう。シベリアにおけるウイルス感染から語り手を変えながら、カリフォルニアの安楽死パーク、場所も定かでない暗闇での目覚め、そして次の次の章ではエレジーホテルへ。こうした構成はまとまりを欠いてもおかしくないところだが、それが見事につながっていくのは、語り手がそれぞれに、パンデミックが生む特殊な状況のなかで、他者とこれまでにない新たな関係を築くことで、死と向き合っていくからだが、詳しいことは「その2」で書くことにしたい。
《参照/引用文献》
● 『闇の中をどこまで高く』セコイア・ナガマツ、金子浩訳(東京創元社、2024年)
● 『人間らしい死にかた――人生の最終章を考える』シャーウィン・B・ヌーランド、鈴木主税訳(河出書房新社、1995年)
● 『How We Live』Sherwin B.Nuland (Knopf Doubleday Publishing Group, 1998)
● 『死体はみんな生きている』メアリー・ローチ、殿村直子訳(日本放送出版協会、2005年)
● 『The American Way of Death Revisited』Jessica Mitford (Vintage; Reprint版, 2000)
● 『Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experience』Pim van Lommel (HarperOne; Reprint版, 2011)
[amazon.co.jpへ]
● 『闇の中をどこまで高く』セコイア・ナガマツ、金子浩訳(東京創元社、2024年)
● 『人間らしい死にかた――人生の最終章を考える』シャーウィン・B・ヌーランド、鈴木主税訳(河出書房新社、1995年)
● 『How We Live』Sherwin B.Nuland (Knopf Doubleday Publishing Group, 1998)
● 『死体はみんな生きている』メアリー・ローチ、殿村直子訳(日本放送出版協会、2005年)
● 『The American Way of Death Revisited』Jessica Mitford (Vintage; Reprint版, 2000)
● 『Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experience』Pim van Lommel (HarperOne; Reprint版, 2011)