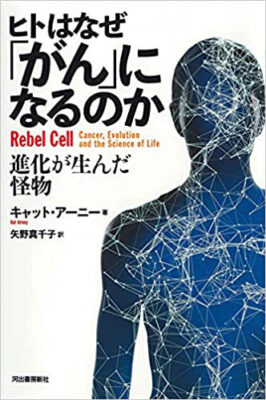最近、読んだからすま和田クリニック院長/京都大学名誉教授、和田洋巳著『がん劇的寛解 アルカリ化食でがんを抑える』について。
第2章「劇的寛解例に学べ」で詳述される「天寿がんが物語る真実から見えてくる新たな視点」が、本書のポイント1とするなら(前の記事「″天寿がん”と二者択一の標準がん治療からの脱却――アシーナ・アクティピス著『がんは裏切る細胞である』と和田洋巳著『がん劇的寛解』を結びつけるもの」参照)、ポイント2になるのは、第3章「がんの正体」で綴られる「がんの正体」だろう。
その「がんの正体」を読んでいてすぐに思い出したのが、サイエンスライター、キャット・アーニーが書いた『ヒトはなぜ「がん」になるのか――進化が生んだ怪物』のことだった。こちらにも同じことを書いた部分があるのだが、興味深いのは、それが「がんの正体」ではなく、一側面であるかのように扱われていることだ。
アーニーはがんを進化視点でとらえているので、がんの始まりも自然選択と深く結びついている。「がんが始まるのは、一定数の変異を拾った細胞が無秩序に増え出すときではない。細胞が、多細胞社会のルールを守らなくても生きていけるような変異を拾い、環境への適応度が上がって周囲の細胞より増えるようになったとき、がんが始まるのだ」
そして注目したいのが、第7章「がんの生態系を探索する」にある以下のような記述だ。
「急速に増えるがん細胞は、無秩序に血管をつくるせいで周囲が低酸素になるため、代謝経路を「解糖系」という別のシステムに切り替えることがある。これは酸素のない太古の海に暮らしていた細菌が進化させたのと同じ代謝経路で、正常細胞より一〇倍も速くグルコースを燃やす。そして排せつ物を乳酸としてまき散らすので、健全だった周囲の環境を有毒な荒れ地に変える」
さらに、「解糖系への切り替えは、ワールブルク効果として知られる」という記述がつづく。
この引用にある「~に切り替えることがある」という表現は、一側面を意味しているが、和田の『がん劇的寛解』では、これが「がんの正体」になるのだ。
それをまとめると以下のようになる。
ヒトの細胞は栄養源となるブドウ糖を取り込んだ後、まず初めに「解糖」というシステムによって、1つのブドウ糖を2つのピルビン酸に分解し、ミトコンドリアに渡す。ミトコンドリアは酸素を用いて受け取ったピルビン酸を水と二酸化炭素に分解することでエネルギーを産生(ATP合成)する。それを「酸化的リン酸化」と呼ぶ。この「解糖」と「酸化的リン酸化」には、「解糖」に酸素は不要という点で決定的な違いがある。
そこで、不摂生などのために血管の内径が細くなると、酸素を運ぶ赤血球は流れにくくなるのに対して、栄養を運ぶ血漿は液体成分なので流れ、「酸素は欠乏しているが、栄養は豊富にある状態」に陥る。
するとどうなるか。臓器細胞が酸素欠乏によって栄養をエネルギーに変えられずに次々とアポトーシスしていくなかで、酸素が欠乏している状態でも解糖だけで栄養をエネルギーに変えて生きていくことのできる細胞が出現する。そんな細胞こそが、分子生物学の分野から見た「がんの正体」だという。
この現象を実験によって世界で最初に証明したのが、ドイツの生理学者で医師のオットー・ワールブルクで、1956年に「がん細胞の起源」という画期的な論文を発表した。そこでこれらの性質や現象は「ワールブルク効果」と呼ばれている。
がんを遺伝子変異や自然選択から捉えるか、代謝から捉えるかによってそこに異なる景観が浮かび上がってくるが、代謝から捉える視点に俄然興味が湧いてきた。次は、和田が本書で参照しているボストン大学の生物学/遺伝学/生化学教授、トーマス・シーフリードに注目してみたい。
▼ 「“代謝疾患としてのがん”に関するトーマス・N・シーフリード教授へのインタビュー」
《参照/引用文献》
● 『ヒトはなぜ「がん」になるのか――進化が生んだ怪物』キャット・アーニー著、矢野真千子訳(河出書房新社、2021年)
● 『がん劇的寛解 アルカリ化食でがんを抑える』和田洋巳(KADOKAWA、2022年)
[amazon.co.jpへ]
● 『ヒトはなぜ「がん」になるのか――進化が生んだ怪物』キャット・アーニー著、矢野真千子訳(河出書房新社、2021年)
● 『がん劇的寛解 アルカリ化食でがんを抑える』和田洋巳(KADOKAWA、2022年)