ジャーナリストのマイケル・ポーランが書いた上下巻からなる『人間は料理をする・上: 火と水』『人間は料理をする・下: 空気と土』では、料理が行われている様々な場所に著者が足を運び、専門家から手ほどきを受けて自らも料理を行うことで、人間と料理の関係が根本から見直されていく。ポーランは料理することによる四つの変化を、自然界の四大元素と結びつけ、1部の火ではバーベキュー、2部の水では煮込み、3部の空気ではパン、4部の土では発酵を扱う構成をつくりあげている。
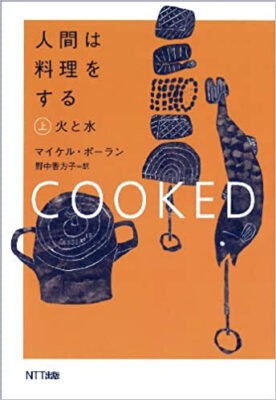
ポーランは、かつて家庭で普通に行われていた料理が、今日では特殊な料理になってしまい、わたしたちにできる料理が限られたものになってしまっていることに対して問題意識を持っている。
「このことは知識の喪失だけでなく、ある種の力の喪失も意味する。そして十分ありえそうなことだが、次の世代では、生の素材から料理することが、今日のわたしたちにとってのビールの醸造やパン作り、ザワークラウトの仕込みのように、きわめて特殊で珍しいことと見なされるようになるかもしれないのだ。
そうなったとき、つまり料理という素晴らしい創造物の作り方を知る人がいなくなったとき、食べ物はその背景である人間の手のみならず、自然界、想像力、文化、そして社会から、完全に切り離される。実際、すでに食べ物は抽象的な存在――体を動かす燃料、あるいは単なるイメージ――になりつつある」
それは重要な問題だが、今回筆者が関心を持ったのは、その主要テーマとは少し違う部分だ。以前の記事「ヒトは料理で進化した、ではその「料理」とは火の使用と発酵のどちらから生まれたのか――リチャード・ランガム『火の賜物』VS.マリー=クレール・フレデリック『発酵食の歴史』」と本書には、深く結びつくところがある。ポーランもヒトが料理で進化したことを重視し、その料理として火の使用と発酵の両方を掘り下げている。しかも、1部の火では、ランガムの『火の賜物―ヒトは料理で進化した』を引用するだけでなく、ランガム自身から直接話を聞き、4部では、ブログで筆者が何度も引用しているサンダー・エリックス・キャッツから発酵の手ほどきを受ける。そうなると、ポーランが火の使用と発酵をどのようにとらえるのか、がぜん興味がふくらむ。
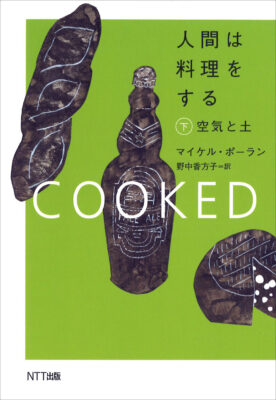
ポーランにとって、火の使用と発酵には温度差がある。思い出したいのは、先ほどの引用のなかで彼が、わたしたちにとってビールの醸造やパン作り、ザワークラウトの仕込みは、きわめて特殊で珍しいことと見なされていると書いていたことだ。ポーランは身をもってその隔たりを示している。
1部の火で扱う料理はバーベキューで、ポーランはそれに慣れ親しんでいる。だから、伝統的なバーベキューを体験するにしても、土台はすでにできている。そして、料理のはじまりとしての火の使用もすんなりと受け入れられるのだろう。この1部ではランガムの仮説が細かく紹介されている。
「ホモ・エレクトスが二足歩行していた時代に、人類が料理をしていたことを証明する化石の証拠は、まだ見つかっていない[ランガムは、ホモ・エレクトスの登場を一九〇万年前から一八〇万年前と見ている]。しかし、この仮説は近年、信憑性を増している。ランガムがその本を出版したとき、火の使用を示す最古の化石はおおよそ七九万年前のものだった。しかしランガムの仮説が正しければ、料理はそれより少なくとも一〇〇万年早く始まっているはずだ」
ポーランは、「少なくとも現時点では、ランガムの主張はすべて推論に基づくものだ」と断ってはいるものの、この導入部では料理のはじまりとは火の使用であることが強く印象づけられる。
では、4部の土で扱う発酵についてはどうだろうか。たとえば、サンダー・エリックス・キャッツ(※本種ではキャッツではなくカッツと表記されている)をアドバイザーにして進められるザワークラウトの仕込みにはかなり苦労しているようにも見える。その結果は以下のように綴られている。
「しかし、実を言えば、ザワークラウトはあまりおいしくなかった。腐敗臭は消えていたが、灰色カビ菌の嫌な菌糸が、周辺部から出ていた。カッツの助言に従って、慎重にそれを取り除きながら、湧きあがってくるおそらくは直感的な嫌悪感を無視しようとした。しかし、その菌はかなり長くそこにいたらしく、ザワークラウトのシャキシャキ感はほとんどなくなっていた」

ちなみに、筆者はキャッツの『サンダー・キャッツの発酵教室』に触発されて、ザワークラウトにはまり、もう何度も仕込んでいるが(「『サンダー・キャッツの発酵教室』に触発されて、キャベツと塩だけでできる自家製ザワークラウトづくりにはまり、常備するようになった」)、そんなふうになったことはただの一度もなく、すべておいしく食べ切っている。
話を戻すと、その後、キムチやピクルスがうまくいったポーランは、キャッツの導きで、腸内細菌叢を研究する科学者と話をするようになり、進化とも関わる以下のような結論に至る。
「つまり進化的に見れば、生化学的戦争において人間よりはるかに経験豊かな細菌たちと手を結ぶのは、人間にとって理にかなった戦略なのだ。複雑な多細胞生物が出現する前に、二〇億年にわたって自然淘汰を経てきた細菌たちは、その過程で、発酵から光合成まで、ほぼすべての重要な代謝の仕組みを自ら編み出してきた」
そこで筆者が注目したいのが、以下のような記述だ。
「しかし、どうしてわたしたちは、発酵食品の複雑なはたらきや腸内細菌との関係に気づくのにこれほど長くかかったのだろう。答えは簡単だ。それらは文字どおり、目に見えないからだ」
「人間のために神から火を盗んだのはプロメテウスだが、では、ピクルス作りのプロメテウスは誰だろう? それを伝える神話がないのだとしたら、それは、大きな動物を焼くのに比べて、野菜や穀物を発酵させることは、自然に立ち向かう英雄的な行為には見えないからなのかもしれない(はなばなしい場面にも欠ける)。しかし人類にとって、発酵に精通したことは、種として成功するうえで、火の支配に匹敵するほど重要だったと言えるだろう(とりわけカッツは、そう主張する)」
それに付け足すなら、マリー=クレール・フレデリックも『発酵食の歴史』で、「初めに発酵ありき」と主張している。
微生物の活動は見えないから、神話にもならないのかもしれないが、時間を大きくさかのぼれば、逆に見えないからこそ、視覚だけに頼らない感覚や直感が研ぎ澄まされ、料理として受け継がれてきたともいえるだろう。それがどこまでさかのぼれるのかも気になるところだ。
《参照/引用文献》
● 『人間は料理をする・上: 火と水』マイケル・ポーラン 野中香方子訳(NTT出版、2014年)
● 『人間は料理をする・下: 空気と土』マイケル・ポーラン 野中香方子訳(NTT出版、2014年)