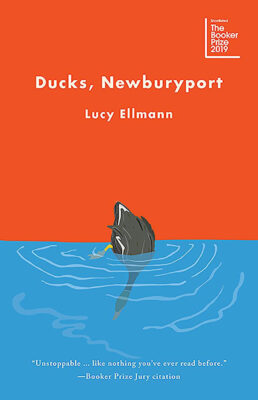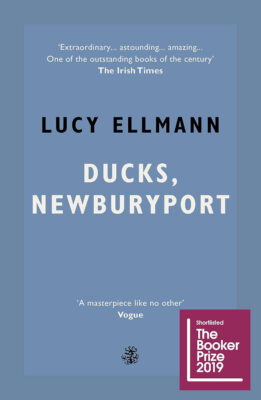[読みたい本についてのメモ] ルーシー・エルマン(Lucy Ellmann)は1956年、米イリノイ州エバンストン生まれで、スコットランドのエディンバラ在住。1988年に発表したデビュー作『Sweet Desserts』は、ガーディアン・フィクション賞(2016年に廃止)を受賞した(1999年に『スウィート』として邦訳出版されている)。その後の作品は、『Varying Degrees of Hopelessness』(1991)、『Man or Mango? A Lament』(1999)、『Dot in the Universe』(2003)、『Doctors & Nurses』(2006)、『Mimi』(2013)など。
1999年発表の本書『Ducks, Newburyport』は、エルマンが7年かけてまとめ上げた長編で、ペーパーバック版ではなんと1020ページ。主人公=物語の語り手は、米オハイオ州の郊外に暮らす主婦だが、彼女について説明する前に、まずは本書の特異な構成や文体に言及しておくべきだろう。本書には明確な筋書きはなく、物語はほぼ彼女の”意識の流れ”で綴られていく。「the fact that ~(~という事実)」から始まる比較的短い文章が延々と積み重ねられ、物語になっていく。ちなみにほぼ意識の流れと書いたその「ほぼ」が何を意味するかといえば、たまに雌ライオンの視点に切り替わるということだが、それは実際に読んでみないと想像もつかないだろう。
名前も定かではない語り手の主婦は、レオという夫と4人の子供たちとオハイオ州の郊外に暮らしている。彼女はかつて小さな大学で非常勤講師をつとめていたが、癌であることがわかり、治療のために仕事をやめ、回復後は家にいて、最近では地元のレストラン向けに自宅でパイを焼いている。その作業と子供たちに振り回される日常のなかで、意識の流れが無限につづくような物語を紡いでいく。
ということで、試しにKindle版のサンプルを読んでみた。長大な作品なのでサンプルとはいえそれなりのボリュームがあり、独特の世界に入り込める。
シナモンロールを焼くための作業をしながら、語り手の意識の流れは、彼女の日常生活における些細な出来事、記憶や夢、観たり読んだりした映画や本のことから、地球温暖化や気候変動、大気や河川や食品の汚染の問題、トランプ政権や銃乱射事件などの犯罪まで、めまぐるしく変化しながら現代ならではの不安を浮かび上がらせていく。また、奔放な連想がときとして韻を踏んでいるだけの単語の羅列になることもある。
この語り手の個人的なことについていえば、彼女は非常にシャイな性格で、いまはパイ作りと子育ての重労働で腰の痛みに悩まされ、彼女の母親の病気と死から立ち直ることができずにいる。大学の非常勤講師として歴史を教えていたので、おそらくその分野には詳しい。映画や本もたびたび引用する。アーミッシュの歴史に触れる部分では、ハリソン・フォード主演の『刑事ジョン・ブック 目撃者』のことも取り上げる。『大草原の小さな家』で知られるローラ・インガルス・ワイルダーの人生や世界に憧れを抱いているように見える。サンプルの終盤には、彼女の最初の夫にまつわるエピソードも出てくる。彼女の長女ステイシーは、その最初の結婚で生まれた子供で、彼女は成長したステイシーとの間に溝があり、関係に悩んでいる。
一方で、息子のベンが生態系や気候変動やパンデミックに強い関心を持っているため、彼から、地球上の哺乳類の半分が2050年までに死滅するとか、全人類がSARSやエボラ、インフルエンザなどによって滅ぶというような予測や警鐘を吹き込まれている。彼女自身も、クジラに蓄積するPCBやオハイオ川に流されていた大量のPFOA(有機フッ素化合物)やオピオイド・エピデミックの問題を意識し、あるいはマクロファージのことを持ちだすなど、そこには、分子レベルや細胞レベルの視点も盛り込まれている。トランプ政権については、トランプ大統領が、オバマケアに加入したオハイオ州民63万人から保険を奪おうとしているとか、すべての国立公園での採鉱と石油掘削を望んでいるといった話題が頭をよぎる。こうしたテーマがこの先、さらに掘り下げられていく。トランプ時代への視点という意味では、リチャード・パワーズの『惑う星』やバーバラ・キングソルヴァーの『Unsheltered』との比較しても興味深いのではないかと思える。
そして、ここで思い出しておきたいのが、アミタヴ・ゴーシュの『大いなる錯乱――気候変動と<思考しえぬもの>』ことだ。なぜ現代小説は、気候変動という題材をさばき、渡り合うことができないのか。地球規模の気候変動をとらえるためには、集団としての人間の存在や想像力がきわめて重要になるが、現代小説において<集団的なるもの>はどのような位置を占めているのか。
「事実として、現代小説はますます徹底的に個人の心理(サイキ)に的を絞ってきている一方で、小説のみならず文化全般にわたる想像力の次元で<集団的なるもの>――「群集としての人間」――が後退局面にあることは認めざるを得ない」
ほぼ語り手の意識の流れだけで語られる『Ducks, Newburyport』は、まさに「徹底的に個人の心理に的を絞った」現代小説のように見えるが、実はそれを逆手にとり、無限につづくような意識の流れを駆使することで、個人を突き抜けて集団的不安を生みだそうとしているのではないか、そんな期待を抱かせる。いつになるやらわからないが、読了したらまた記事にしたい。
最後に、おまけの動画レビューを。
▼ 『Ducks, Newburyport』ルーシー・エルマン著/レビュー&シナモンロールのレシピ
レビュアーが文学通のようなので、注目する部分が筆者とは少し違うが、小説の全体像をイメージするのに参考になる。個人的にジョイス・キャロル・オーツがけっこう好きなので、この先の物語で彼女にも言及されることがわかり、さらに興味が増した。
《参照/引用文献》
● 『Ducks, Newburyport』(Kindle版)Lucy Ellmann (Galley Beggar Press, 2019)
● 『大いなる錯乱――気候変動と<思考しえぬもの>』アミタヴ・ゴーシュ著、三原芳秋・井沼香保里訳(以分社、2022年)
[amazon.co.jpへ]
● 『Ducks, Newburyport』(ペーパーバック版)Lucy Ellmann(Biblioasis、2019)
● 『Ducks, Newburyport』(Kindle版)Lucy Ellmann (Galley Beggar Press, 2019)
● 『大いなる錯乱――気候変動と<思考しえぬもの>』アミタヴ・ゴーシュ著、三原芳秋・井沼香保里訳(以分社、2022年)