「社会科学の視点でとらえたHIVから自然科学の視点でとらえたHIVへ――ランディ・シルツ著『そしてエイズは蔓延した』からデビッド・クアメン著『スピルオーバー』へ その2」を書いているときに、進化生物学者にして医師でもあるフランク・ライアンが書いた『破壊する創造者 ウイルスがヒトを進化させた』(2009年の著書で邦訳は2011年)のことを思い出した。本書でライアンが提示しているのは、突然変異と自然選択に、「共生」や「異種交配」という別の要素を加えた「新しい進化論」。ウイルスが、ヒトを含む生物の進化にきわめて重要な役割を果たしているということだ。
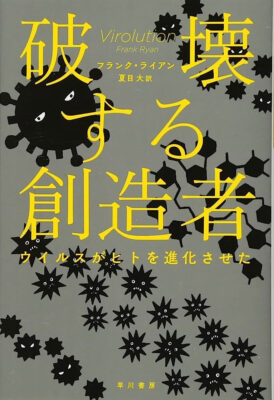
デビッド・クアメンの『スピルオーバー――ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び移るのか』のなかで、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)を扱った第Ⅷ章「チンパンジーと川――HIV」と本書のなかで、HIVを扱った第四章「AIDS(エイズ)は敵か味方か」には興味深い接点があり、対比してみるとクアメンとライアンの視点の違いがより明確になる。
本書の第四章の導入部でも、『スピルオーバー~』と同じようにランディ・シルツの『そしてエイズは蔓延した』が引用されている。「本の中には、AIDSが流行し始めた時の人々の混乱、偏見、戸惑い、責任をなすり合う様子、そして、一部の医師や科学者の献身的な努力などが描かれている。また、政府や主要関係機関のひどい不手際、不十分な対策、対応の遅れなども指摘されている。大変な悲劇だ」。というように、やはり社会科学的な視点を踏まえたうえで、自然科学的な視点へと移行する。
さらにその先で、クアメンとライアンは、マックス・エセックス教授という同じ研究者に注目する。クアメンの本では、米ハーバード公衆衛生大学院のがん生物学の教授だった獣医学博士、ライアンの本では、ハーバード大学エイズ研究所の所長で、癌生物学部門のリーダーと紹介されている。

冒頭でリンクを張った記事のなかで、研究者の名前まで書かなかったが、以下の記述「ニューイングランド霊長類研究センターで飼育されているサルが、謎の免疫不全に陥り、死んでいた。1985年、そのサルの血液サンプルからレトロウイルスが発見され、それがエイズの原因ウイルスの近縁だと判明し、最終的にHIVとの類似性から「サル免疫不全ウイルス」(SIV)とされる」「アフリカからもエイズの報告があり、起源に関する疑問の焦点はアフリカに移る。セネガルの売春婦たちから検出された新しいウイルスは、既知のHIVよりもアフリカミドリザルのSIV株により近かった。そこで既知のウイルスが「HIV‐1」となり、新しく発見されたものが「HIV‐2」になる」は、そのエセックス教授と、博士課程の学生フィリス・J・カンキが解明したことである。
さてそこで、筆者が興味を覚えたのは、クアメンとライアンそれぞれの関心と、エセックス教授の研究についての位置づけの違いだ。ライアンはエセックス教授に関心を持ったきっかけを以下のように綴っている。
「私がある雑誌に目を留めたのは一九九五年初めのことだった。『サイエンティフィック・アメリカン』誌の記事だ。その時点で掲載されてから八年ほど経っていた。すでにAIDSは大流行しており、皆が騒いでいる只中で書かれた記事である。(中略)記事のタイトルは、「AIDSウイルスの起源」だった。このタイトルだけでは興味を惹かれなかったかもしれないが、問題は、「AIDSウイルスは特別な存在ではない」という言葉で始まるサブタイトルだった。本文を読んでいくと、そこには、「今や悪名高いHIV-1には、実は人間や、熱帯雨林のサル、類人猿を宿主とする親戚が多く存在する」ということが書かれていた。そして、何より驚いたのは、そうした「親戚」のレトロウイルスの中には、すでに何の病気も引き起こすことなく宿主と共存できるよう進化、適応しているものがあるという話だ」
クアメンであれば間違いなくタイトルに反応しただろう。人獣共通感染症(ズーノーシス)をテーマに掲げた彼が明らかにしようとしたのは、悪名高いHIV-1グループMの起源だからだ。また、クアメンもHIV-1の親戚には反応しているが、彼が驚くのは、異種間伝播(スピルオーバー)が何度も起こっていることであって、宿主との共存や進化ではない。その違いは、エセックス教授との関係にも表れている。
クアメンもライアンも関心を持った研究者には、直接会いに行って、積極的に話を聞く。だが、クアメンの場合は、HIV-1グループMの起源が最大の目的なので、エセックス教授については特に話を聞くことはなく、その起源に迫ろうとする別の研究者たちを取り上げていく。これに対して、ライアンはエセックス教授にインタビューを申し込み、第四章の後半はふたりの対話が中心になる。
その対話の前半は、先述したような、エセックス教授が解明したSIVやHIV-2の確認だが、後半でそこからさらに踏み込んだ話になる。アフリカのマンガベイ属のサルはSIVに感染していても病気の徴候は出なかった。これに対して同じ施設に収容されていたアジアのマカクは病気にかかった。そこからライアンは仮説を立てる。あるウイルスがある動物に感染してから長い時間が経過し、病気を引き起こすことなく共存できる状態に達する。その後、よく似た別の動物が接触し、非常に近い異種間でウイルス感染が起きると、ウイルスは凶悪なふるまいをするようだ。それは、ウイルスと宿主との共生関係によって進化したメカニズムなのではないか。よく似た種の動物は、食べ物などをめぐってライバルとなることが多いので、ウイルスが種を越えて感染し、侵入者を排除してくれれば利益になるのではないか。
エセックス教授はそれを理に適った仮説として受け入れ、オーストラリアのウサギと粘液腫症の話を持ち出す。オーストラリアのウサギは元々、ヨーロッパ人が持ち込んで飼っていたものだが、一部が野生化し、大繁殖し、農作物を荒らし始めた。そこでウサギを退治するために持ち込まれたのが、これまでそのウサギたちが出合ったことがない粘液腫症のウイルスで、急激に感染が広がり、全体の99.8%が死んだ。だがその後、ウイルスに耐えて生き残ったウサギが急速に繁殖し、以前と変わらない数に戻った。生き残ったウサギの身体にはウイルスが残っていた。
教授はこのように話をつづける。「宿主とウイルスが、状況によってお互いへの攻撃性を弱める場合がある、ということの明らかな証拠だと私は思いました。そうすることで、両方が生存できる可能性を最大限に高めるのです。そこへ仮にまた別のウサギを連れてきたとすると、元からいるウサギより不利になります。生き延びたウサギたちはもはやウイルスと共存している状態で、粘液腫症のウイルスを持っていても健康な身体のまま生きていられます。ところが、その同じウイルスは、別の、ライバルとなり得るウサギにとってはやはり毒性が強く、脅威となるのです」
さらに、サルの種を越えて感染すると毒性が強くなるヘルペスのウイルスについてライアンが尋ねると、以下のような答えが返ってくる。「特に顕著な例はリスザルヘルペスウイルス(Herpesvirus simiri)とクモザルヘルペスウイルス(Herpesvirus anteles)でしょう。どちらも、リスザル、クモザルという特定のサルとともに共進化してきたウイルスです。そして、どちらのウイルスも、別のサルに感染した場合、非常に致死性が高いのです。しかし、通常の宿主であるリスザルやクモザルには何もしません」
ふたりの対話はもっとずっと長いが、ライアンはエセックス教授の発言を踏まえて、「私たちが、存在も知らない多くのウイルスに感染しているとしても不思議ではない」としたうえで、彼が「攻撃的共生」と呼ぶ関係の変化の過程を以下のように説明する。
「だが、時には、ウイルスが、新たな宿主と良好な関係を結べないこともある。粘液腫症ウイルスがオーストラリアで野生化したウサギに感染した時や、HIVが人間に感染した時がそれにあたる。最初に粘液腫症ウイルスに接触したオーストラリアのウサギの九八・八パーセント、最初にHIVに接触したヒトの九八パーセントほどが間もなく死亡している。そこまでが攻撃的共生の第一段階である。新たな宿主に侵入したウイルスは、共に生きることのできない者をすべて殺してしまう(後略)」
「(前略)当たり前だが、死亡率が高ければ、その分だけ、新しい宿主の数が減少してしまうことになる。そして生き残った集団が全体として持つ遺伝子の構成は、感染前の集団のそれとは違ったものになるだろう。生き残った個体も完全に健康ではない可能性があるし、寿命がやや短くなるということもあり得る。だが、ここで重要な意味を持つのは、ともかく個体が生き残れば、その体内でウイルスも生き延びられるということだ。こうして、生き続ける宿主とウイルスが長期にわたって共進化し、やがて「相利的」な関係を築いていく、それが、攻撃的共生の第二段階ということになる」
筆者がここで注目したかったのは、デビッド・クアメンとフランク・ライアンのHIVやエイズに対する関心、あるいは好奇心の違いから見えてくるものなので、本書の第四章より先に進むことはしない。生物学者/作家/ノースカロライナ州立大学教授のロブ・ダンは、『家は生態系 あなたは20万種の生き物と暮らしている』のなかで、科学者の好奇心について以下のように書いている。
「チャンスは心の準備ができている者のところにやって来る、とよく言われるが、それ以上にチャンスに好かれるのは、何かに取り憑かれている者だ。何かに取り憑かれた状態というのは、科学者にとってはごく自然なことで、何かに対して集中的に、執拗なまでに好奇心を向けたときに現れる。しかし、科学者に限らず、どんな人間にもその可能性は開かれている」
こうした心の準備や好奇心は様々なかたちで表現される。心臓専門医のユアン・アンガス・アシュリーは『ゲノム・オデッセイ』でそれを、シャーロック・ホームズのミステリを引用しつつ説明しているといえる(「ゲノム医療の可能性を切り拓いた医師や研究者と確定診断を求めてさまよう患者や家族たちのオデッセイ(苦難に満ちた長旅)――ユアン・アンガス・アシュリー著『ゲノム・オデッセイ』」参照)。
そして、デビッド・クアメンもフランク・ライアンもそれを持っているが、マックス・エセックス教授の研究に関していえば、ライアンにとってひとつのチャンスになっている。
「『ウイルスX』を出版した後も、私は調査を継続したが、その中で、ウイルスを共生者とみなすべきという確信はどんどん強くなっていった。そして、AIDSの特性について詳しく調査したことで、ウイルスを共生者とみなす考え方が、人間という生物を理解する上でも重要だということに気づき始めた。特に、マックス・エセックス教授へのインタビューで、種を越えたレトロウイルスの感染について話し合ったのがきっかけとして大きかった」
《参照/引用文献》
● 『破壊する創造者 ウイルスがヒトを進化させた』フランク・ライアン 夏目大訳(早川書房、2011年)
● 『スピルオーバー――ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び移るのか』デビッド・クアメン 甘糟智子訳(明石書店、2021年)
● 『家は生態系 あなたは20万種の生き物と暮らしている』ロブ・ダン 今西康子訳(白揚社、2021年)
● 『そしてエイズは蔓延した』ランディ・シルツ 曽田能宗訳(草思社、1991年)
[amazon.co.jpへ]
● 『破壊する創造者 ウイルスがヒトを進化させた』フランク・ライアン 夏目大訳(早川書房、2011年)
● 『スピルオーバー――ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び移るのか』デビッド・クアメン 甘糟智子訳(明石書店、2021年)
● 『家は生態系 あなたは20万種の生き物と暮らしている』ロブ・ダン 今西康子訳(白揚社、2021年)
● 『そしてエイズは蔓延した』ランディ・シルツ 曽田能宗訳(草思社、1991年)