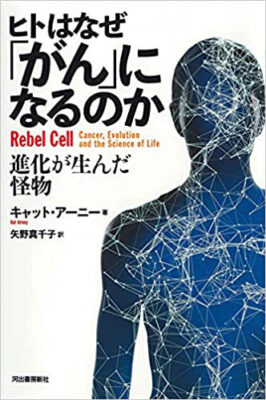「自然界の生物が飢餓や捕食者といった選択圧を受けて進化するのと同じように、がん細胞も人体という生態系の中で選択圧を受けて進化する」。がんを進化視点で考えるキャット・アーニーの『ヒトはなぜ「がん」になるのか――進化が生んだ怪物』(2020年/邦訳2021年)には、興味深い研究や治療を行っている研究者や医師が取り上げられているが、UCLがん研究所/フランシス・クリック研究所の教授で、肺がんを治療する腫瘍内科医でもあるチャールズ・スワントン(Charles Swanton)もそのひとりだ。
この記事は、以前の記事「進化とともに生きる――キャット・アーニー著『ヒトはなぜ「がん」になるのか』とロブ・ダン著『ヒトという種の未来について生物界の法則が教えてくれること』の併読から見えてくるもの」のつづきともいえる。
がん細胞も自然選択によって進化するという考え方そのものは、1976年に科学者ピーター・ノウェルが『サイエンス』に発表した短い論文「腫瘍細胞集団のクローン進化」や、2000年にがん生物学者メル・グリーヴスが書いた『がん――進化の遺産』など、以前から存在していたが、あまり注目されなかった。
では、いつその風向きが変わったのか。アーニーによれば、それは2012年、チャールズ・スワントンが『ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』誌に、がんの進化と不均一性に関する論文を発表したときだった。その論文は一躍注目の的となり、世界中の主要な研究活動に取り上げられたという。
ではそれは、どのような研究だったのか。ここでは、本書だけでなく、動画も参照してその研究に注目してみたい。スワントンは、「時空を超えるがんの進化」という講義の動画で、視覚化されたデータを使って自らこの研究について解説しているので、本書と動画の両方を参照するとよりわかりやすくなる。
▼ 「時空を超えるがんの進化」と題されたチャールズ・スワントンによる講義(ランチアワー・レクチャーズ)
まず注目したいのは動画。2002年から2008年にかけて、スワントンがまだ医学生だった頃、腫瘍学の研修において、がんは突然変異した一個の細胞から直線的に進化すると教えられたという。腫瘍内の細胞はどれも同じなので、どの部分で生検を行っても結果は同じになる。もしそれが本当なら、なぜがんの治療はこれほど難しいのか。彼が行った最初の大規模な実験は、そんな疑問から出発した。
そこで、あるがん患者の症例へと話が進むが、それはアーニーが本書で便宜的に「イヴィ」と呼んでいる患者と重なるので、同じ研究の説明をしていることがわかる。
「イヴィのがんは、片方の腎臓ほぼすべてを占めるほど大きく育っており、もう片方の腎臓にも広がっていた。肺には二次性の腫瘍があちこちにできていて、胸壁にはとくに大きな腫瘍が根を張っていた」
「スワントン率いる研究チームは切除された腫瘍を回収し、遺伝子解析をするためのサンプルに切り分けた。大きな原発腫瘍から九つ、胸壁腫瘍から二つ、そしてもう片方の腎臓に広がっていた小さな二次性腫瘍をまるごとだ」
そして、それぞれの腫瘍サンプルに見つかった変異をカタログ化し、それらの腫瘍がたどった進化経路を系図化した。「どの腫瘍も互いに似ていて同じ変異をたくさん有していた。だが、全部同じ変異を共有している腫瘍はなく、一つひとつすべて違っていた。すぐ隣に位置していた腫瘍でさえ若干の差異がある。離れたところで成長していた腫瘍は、原発腫瘍の変異とかなり違っていた」
動画を見ればわかるように、スワントンが描き出したがんの進化系統樹は、かつてダーウィンが描いたものに非常によく似ていた。がん細胞は直線的ではなく、枝分かれして進化していた。この患者は、外科手術の前に、分子標的薬(mTOR阻害薬)であるアフィニトール(一般名エベロリムス)を6週間投与されていたが、このがん細胞の多様性によって薬剤反応の不均一性があらわれていた。
スワントンは、この大きな原発腫瘍の生検を、自然界、ケニアからタンザニアにかけての広大な領域における生態的多様性の調査に例えている。生検によって腫瘍の全体像を把握したと結論づけることは、ケニアのマサイマラ保護区からタンザニアのンゴロンゴロ自然保護区に至る250キロの回廊のなかの10メートルを取り出して調べ、回廊全体の多様性の地図を作るようなものだというのだ。
このがんと自然界を結びつける例えは、ダーウィンを意識しているのだろうが、確かにがんの治療の難しさは、自然界と対比してみることで鮮明になる。本書の以下の記述にもそれが当てはまる。
「地球規模で見れば、進化は地球上に生物種のみごとなまでの多様性をもたらしてくれた。しかし、腫瘍内で繰り広げられる多様性は私たちにとって厄介で、進行がんの治療を困難にする。自然界では、ある生物種に遺伝子多様性があればあるほど、過酷な状況に直面しても一部の個体群が適応できるので、種としての存続を可能にする。
がんの場合、放射線治療や化学療法、分子標的薬による猛攻撃が選択圧となる。感受性のある細胞は一斉に殺されるが、どこかに潜んでいた耐性をもつ細胞は生き残り、増殖をはじめる。これは治療の失敗というより、進化のシステムが正常に機能している証拠だ。地球上の生物多様性を育んだのと同じ仕組みが、私たちの体内でも働いているのだ」
《参照/引用文献》
● 『ヒトはなぜ「がん」になるのか――進化が生んだ怪物』キャット・アーニー著、矢野真千子訳(河出書房新社、2021年)
[amazon.co.jpへ]
● 『ヒトはなぜ「がん」になるのか――進化が生んだ怪物』キャット・アーニー著、矢野真千子訳(河出書房新社、2021年)
● 『がん―進化の遺産』メル・グリーブス著、水谷修紀監訳(ブレーン出版、2002年)