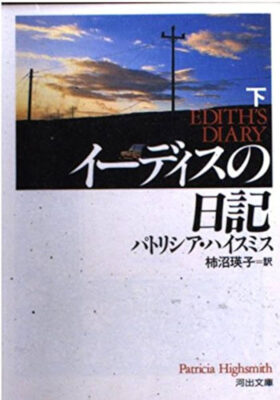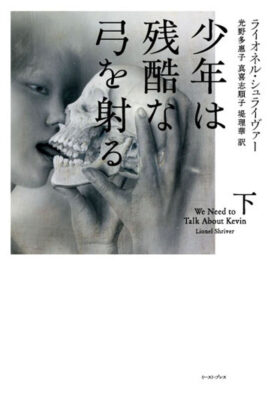前の記事「パトリシア・ハイスミスの『イーディスの日記』とライオネル・シュライヴァーの『少年は残酷な弓を射る』は時を超えてドメスティック・ノワールとして深く響きあう」は当初、2作品ではなく、ギリアン・フリンの『ゴーン・ガール』も加えた3作品を取りあげるつもりだったが、あまりにも長くなってしまうので2作品でまとめた。今回は2作品と『ゴーン・ガール』のつながりに注目する。パトリシア・ハイスミスの『イーディスの日記』(1977)とライオネル・シュライヴァーの『少年は残酷な弓を射る』(2003)と『ゴーン・ガール』(2012)という3作品はそれぞれにドメスティック・ノワールに分類できるだけでなく、興味深い接点と時代による変化が見えてくる。
まず確認するのは、前の記事で細かく触れた2作品それぞれと『ゴーン・ガール』のつながりだが、その前に、前の記事を少し補足しておきたい。『イーディスの日記』と『少年は残酷な弓を射る』の接点について、書き切れなかったことがある。ベトナム戦争のことだ。
『イーディスの日記』では、ベトナム戦争が避けて通れない要素のひとつになっている。物語の背景は、主人公イーディスが夫や息子とともにニューヨークからペンシルバニア州のサバービアに転居する1955年から1975年にいたる時代であり、彼女はその新生活のなかで、若干左寄りの健全なアメリカのリベラリズムを代表するような新しい新聞を発行しようと尽力するからだ。しかしサバービアでの生活のなかで彼女の政治的な姿勢は揺らいでいく。無気力な息子が問題行動を繰りかえし、引き取った夫の伯父の世話に追われ、若い秘書に本気になった夫が家を出るという状況のなかで孤立した彼女は、日記につづる妄想の世界にのめり込んでいく。それはベトナム戦争に対する姿勢にも反映される。「だが数秒間の沈黙のうちに、彼女がいったいベトナムの敗退についてどちらの味方だったのかわからなくなっていた。まるで氷の上であおむけに倒れたような感じだった。なんてことだろう!」
一方、『少年は残酷な弓を射る』の物語の背景になるのは、主に1980年代初頭から2001年にかけての時代だが、独特の構成で物語が語られる。主人公エヴァは、人気の旅行ガイドを手がける会社の経営者で、赤ん坊のころから母親に執拗な反抗を繰り返してきた息子ケヴィンが、1999年に社会を震撼させる事件を起こす。この物語はその事件後、2000年から2001年にかけてエヴァが夫のフランクリンに宛ててつづった手紙だけで構成されている。
その手紙の一通のなかで、「8歳から14歳までのケヴィンのことはなんだかよく思いだせないのよ」という言葉のあとに以下のような文章がつづく。「それでも、鮮明な記憶はいくつかある。とりわけ、仕事に対する情熱をどうしても家族にも共有してもらいたくて、あなたと13歳のケヴィンをベトナムに連れていって、期待はずれな結果になったあの旅行(シーリアはまだ小さかったから、わたしの母にあずかってもらった)。わたしがベトナムを選んだのは、アメリカ人にとって、少なくともわたしたちの世代にとって、特別な意味のある場所だからだった。あそこだったら、はじめて訪れる外国でだれもが陥りやすい『旅の恥はかきすて』の気分にはならないんじゃないかと思ったの。それに、あのころのベトナムは観光誘致に乗りだしたばかりだったから、仕事のためにも行ってみたかった。もちろん、水田や、円錐形の麦わら帽子をかぶったしわくちゃの老女に対する罪悪感のまじった親しみは、あなたとわたしにしかわからないものよね。わたしは20代のころワシントンの反戦デモに参加したし、あなたは、むだを承知で、偏平足を理由に入隊を却下したいよう徴兵局に嘆願に行ったこともあった。わたしたちが出会ったのはサイゴン陥落から3年後で、あの戦争についてずいぶん議論を交わしたわよね。でも、ケヴィンはそういうことには無関係だったから、わたしは自分の予想に反してあの子を『旅の恥はかきすて』という気分にさせてしまったのかもしれない。それにしても、ケヴィンが――とにかく、悪い言葉はすぐに覚える子だった――ハノイの街でスクーターの波をかき分けながら『どけよ、ベトナム野郎(グーク)』というのを聞いたときに感じた恥ずかしさは、一生忘れられないと思うわ」
2作品からこの抜きだした部分だけを対比してもピンと来ないとは思うが、前の記事に書いたような共通点によって、もしシュライヴァーが『イーディスの日記』にインスパイアされていたとすれば、作品全体から見ると少し異質な印象を与えるこの記述は、ある種のオマージュのようなものなのではないかと思えるのだ。
ということで、冒頭で書いたように2作品それぞれと『ゴーン・ガール』のつながりを確認することにする。
まず、『イーディスの日記』と『ゴーン・ガール』の接点から。もうご存じかとは思うが、『ゴーン・ガール』の裏表紙から概要を引用しておく。「ニックは34歳、ニューヨークで雑誌のライターをしていたが、電子書籍の隆盛で仕事を失い、2年前、妻エイミーとともに故郷ミズーリに帰ってきた。しかし都会育ちの妻にとってその田舎暮らしは退屈きわまるものだった。
結婚五周年の記念日、エイミーが、突然、謎の失踪を遂げる。家には争った形跡があり、確かなアリバイのない夫ニックに嫌疑がかけられる。
夫が語る結婚生活と交互に挿入される妻の日記。異なるふたつの物語が重なるとき衝撃の真実が浮かび上がる」
ギリアン・フリンは影響を受けた作家としてパトリシア・ハイスミスの名前を挙げている。特に『ゴーン・ガール』については、ハイスミスの『水の墓碑銘』から直接的な影響を受けたとどこかで語っていたが、個人的には『イーディスの日記』とのつながりも見逃せないと思う。
『ゴーン・ガール』のエイミーとニックもサバービアに転居する。彼らはマンハッタンの景色が一望できるブルックリンのアパートメントに住んでいた。それは、娘をモデルにした児童書『アメージング・エイミー』のシリーズで成功を収めたエイミーの両親が買ってくれたものだった。しかし、ニックが失業し、エイミーの両親もずさんな資産管理の結果、破産同然になっていることが判明する。ただし、それが転居の直接の理由ではない。ニックの母親がステージ4の癌だとわかった。しかも彼の父親は少し前からアルツハイマーを患っていた。それでニックは故郷ミズーリに戻る決心をし、夫婦は、建物は大きく立派だが不況のせいでひどく寂れたサバービア、カーセッジに転居する。
『イーディスの日記』では、イーディスの一家がサバービアに転居して間もなく、夫ブレットの年老いた伯父が同居することになり、寝たきりに近いため彼女が負担を強いられる。さらに、ブレットが若い秘書に本気になり家を出てしまう。『ゴーン・ガール』のエイミーの場合は、直接的にニックの両親の面倒を見るわけではないが、夫とその家族の事情で地方の寂れたサバービアに移った。しかも、ニックが地元にバーを開くために彼女の信託財産を使い果たしたというのに、短大の講師も兼任していたニックは、教え子のアンディと関係を持つようになる。イーディスとエイミーは似た状況で孤立していく。
そしてもうひとつの共通点が、どちらの物語も「日記」が重要な位置を占めているということだ。イーディスが書く日記も、エイミーが書く日記も、事実に基づく記録ではない。孤立したイーディスは、幸せな生活を妄想する。現実の息子クリッフィーは、ソシオパス的な傾向がある落伍者だが、日記のなかでは、彼女の希望の星であり、大学も卒業し、技術者として就職し、良家の娘と結婚する。一方、エイミーは日記に偽りの夫婦関係や個人的な感情をつづっている。そんな日記が果たす役割は対照的ともいえる。イーディスの日記は誰にも読まれることなく封印され、エイミーの日記はやがて公になることを念頭に書かれている。
それでは今度は、『少年は残酷な弓を射る』と『ゴーン・ガール』の接点について。『少年は残酷な弓を射る』にもサバービアへの転居がある。主人公エヴァと夫フランクリンは、ニューヨークのトライベッカのアパートに暮らしているときに、子どもを持つことを考えるようになる。そして、1983年に生まれた息子ケヴィンが、3、4歳になるころに、ハドソン川対岸、ニューヨーク州ロックランド郡にある最近になってできたサバービア、グラッドストンに転居する。そこでケヴィンの妹シーリアが生まれ、4人家族になる(都会が好きなエヴァが転居を望まなかったことは前の記事に書いた)。
ギリアン・フリンが『少年は残酷な弓を射る』を読んでいたかは定かでないが、夫婦の設定や、母親になること、子どもをもつことをめぐる駆け引きには、響きあうものがあるように思える。
たとえば、エヴァは自身の年齢についてこのようにつづっている。「作るんだったらその年8月わたしが37歳になるまでにと決めていたのは、いまから考えたらお笑いぐさだわね。だって、それは自分たちが60歳になったときには子どもが独立して家を離れていてくれなくちゃということで、そこから逆算した期限だったんだから」
ニックはエイミーの年齢についてこのように考える。「エイミーは子どもはいらないと決めていて、幾度もそう宣言していたからだ。でもその涙を見て、ひょっとしたら気が変わったのかと、あきらめ悪く一縷の望みを抱かずにはいられなかった。時間はたっぷりではなかったから。カーセッジに越してきたとき、エイミーは37歳だった。10月には39になる」
この2作品では、エヴァもエイミーも本心では子どもを求めていない。エヴァは、子どもが欲しいフランクリンを深く愛しているため、つくる決心をするが、実際に妊娠や出産となると抵抗をおぼえる。そこに彼女の性格があらわれている。
(妊娠について)「わたしはこのときはじめて知ったのよ、母親になると決まったとたん、自分は公共物になるんだって。公共物、つまり公園の人間版みたいなものよ。よく妊婦にいわれる『あなたはいま、赤ちゃんも含めてふたりのために食べているんですからね』という言い方は、妊婦の夕食はもう個人的な営みではないといっているにほからなないんだわ。アメリカ国歌の『自由の地』という歌詞がどんどん高圧的になっていくように、それはやがて『あなたはわたしたちのために食べてるんですからね』になりかねない」
(出産について)「あなたの終始変わらず希望に満ちた顔にも、その顔がわたしを励ますようにこっちを見ていることにも腹が立った。あなたはこんなに気楽にパパになろうとしているのに、あんなにウサちゃんだのなんだのを買いこんできてのんきにしているのに、雌ブタみたいにふくれあがるのもわたし、お酒を断ったりビタミンを飲んだりしなきゃならなかったのもわたし。かつてはあんなに真ん中に寄ってきれいだった乳房が醜く腫れていくのを見ていなきゃならなかったのもわたし。ホースほどの広さしかない管のなかにスイカの大きさのものを押しこまれて、ズタズタになるのもわたしなのよ。そうよ、そうなのよ。わたしはあなたを憎んだわ」
一方、エイミーには、子づくりに積極的だった(ように見えた)時期がある。彼女がピルはやめたと言ってから3カ月なにも起きなかったので、ミズーリに引っ越してしばらくして彼女自身が不妊治療の申し込みをした。ところが、ニックが求めに応じて精子を提出して協力しているのに、エイミーはなにもせず、薬を服むのもずるずる引きのばした。そして、しびれを切らしたニックとエイミーのあいだにこんなやりとりがつづく。
「(前略)『なあエイミー、子どもを作ろう』と囁くと、エイミーはノーと答えた。狼狽や警戒や不安は予想していたが――『ニック、わたしいい母親になれるかしら』――返ってきたのはにべもないノーのひとことだった。取りつく島もないノー。取り乱しも、騒ぎもせず、もう興味もないというように。『だって、大変な仕事は全部押しつけられるんだって気づいたんだもの。オムツ替えも病院通いもしつけもわたしで、あなたは気が向いたときに楽しいパパ役をやるだけでしょ。ちゃんとした人間に育てる役は全部わたしで、あなたはそれを台無しにしたりするのに、子どもはあなたに懐いて、わたしを嫌うのよ』」
このエピソードは重要な伏線になっているが、ノーにつづくエイミーの言葉には、子づくりを決意したエヴァに起こることが集約されているともいえる。
前の記事も含め、ここまで取り上げてきた接点から3作品をドメスティック・ノワールの系譜と位置づけることができるかと思う。では、それを踏まえて、サバービアを取り巻く外部の世界に対する認識が、それぞれの物語のなかでいかに変化し、さらに時代とともにどう変化するのかを確認してみたい。
『イーディスの日記』において、孤立する以前のイーディスの外部に対する認識を端的に表しているのが以下の記述だ。「イーディスの脳裏に、17歳の夏メラニー伯母さんとヨーロッパ旅行をした思い出がよみがえった。クイーン・メリー号のファーストクラスで二人はサウザンプトンに向かい、それからロンドン、パリ、ローマ、フィレンツェ、ヴェニスと旅して回ったのだ。それはイーディスの人生で最高の二ヵ月だった。そのときの記憶は今でも鮮やかな美しさをもって生き生きと呼び起こすことができる。そのときの旅の詳細を――たとえばフィレンツェで見た、雨に濡れるミケランジェロのダビデ像――を彼女はあとになって日記に書きつづった」
だが、イーディスにとって心の支えだったメラニーも亡くなり、そんな記憶も遠いものになっていく。そこで興味深く思えてくるのが、イーディスと息子クリッフィーの関係だ。クリッフィーは、本来なら自分のものだった部屋を占領する寝たきりの(父方の)大伯父を疎ましく思い、世話するふりをしてコデインを好きなように飲ませ、最後にはその行動が問題になる。イーディスにとって問題行動を繰りかえす息子は悩みの種だったはずだが、同時に不可欠の存在にもなっていく。なぜなら日記につづる妄想の世界では、彼が希望の星になっていくからだ。そんな妄想はどこかで現実にも影響をおよぼし、彼の問題行動に目をつぶるばかりか、かばおうとすらするようになる。そして、閉ざされたサバービアで、希望の星となった息子を通して外部の世界を感じるようになる。
「今やクリッフィーは一週間に一度、仕事のためにニューヨークへ出かけ、デビーと共同で借りているアパートメントで一泊していった。二ヵ月に一度、彼は会議のためにアメリカに帰り、同じ会社のエンジニアたちと(たった今飛び立ってきたばかりの)クウェートで現在彼が手がけている仕事について話し合い、あるいはニュージャージーの我が家にこもり、秘密の発明――会社を除けば誰にも、妻のデビーにさえも打ち明けようとしなかった――に打ち込んでいた」
ということで、これを「サバービアを取り巻く外部の喪失と内なる異国」と呼ぶことにして、さらに系譜をたどってみたい。
『少年は残酷な弓を射る』で、人気の旅行ガイドのシリーズを手がける会社を経営するエヴァが、仕事で旅してきたのはグローバリゼーションが進む世界だ。夫のフランクリンと子づくりについて考えるよになった彼女は、そんな外部の世界と子づくりを以下のように対比する。
「(前略)わたしは旅を続けるうちに、たとえばモロッコに行って家に入るときに靴を脱ぐことになっているのかどうかを気にするより、なるほど、どの国にも靴に関する習慣があるんだなと、そちらに関心が行くようになったの。そう思いはじめると、気候も建物もげっぷや靴に関する習慣もどこにでもあるものだから、わざわざ手荷物を預けたり、時差に慣れたりしながら、苦労してどこかへ行っても、また同じところに到着したようにしか思えなくなってしまった。世界が均一化しているということに関しては、わたしもしょちゅうグローバリゼーションに文句をいっているけど――あなたがいつも履いていた焦げ茶のストーブパイプ型の作業靴だって、いまやバンコクのバナナ・リパブリックでも買えるのよ――、ほんとうに均一化してしまったのはわたしの頭のなかにある世界、つまり世界のことをわたしがどう考えるか、どう感じるか、どう語るか、だったんだわ。だから、ほんとうの意味でどこかちがう場所へ行こうと思ったら、もうちがう空港に降りたつのではだめ。ちがう人生、ちがう生活に旅をしなければならないのよ。
『母親になるという体験が――』と、わたしはあなたにいった。『新しい国なのよ』」
ただし、これはエヴァがケヴィンを産む前の話だ。では、ケヴィンが社会を震撼させる事件を起こしたあと、母親としてそれまでの歩みをどう振り返るのかというと、やはり息子と外部の世界が結びつけられているのだ。
「これと同じような無邪気さで、若いころのわたしも行動してたんだわ――スペインにも木が生えていたといっては落胆し、どんな辺境に行ってもそれなりの食べ物や気候があると知ってはがっかりしていた。わたしはどこかまったく違う世界へ行きたかった。異国を求めることにかけては、わたしの情熱は尽きることがないんだと、愚かにも思いこんでいた。
わたしはケヴィンによって本物の異国を知ったわ。それはまちがいない。だって、異国って、なにがなんでもわが家に帰りたいという焼けつくような願望を抱かせる場所だから」
これは筆者の推測にすぎないが、ハイスミスの『イーディスの日記』にインスパイアされたシュライヴァーは、そこに「サバービアを取り巻く外部の喪失と内なる異国」を見出し、グローバリゼーションの時代を背景にそれを掘り下げてみせたともいえるのではないか。
では、フリンの『ゴーン・ガール』の場合はどうか。そもそも本作の主人公になるエイミーとニックの夫妻には息子はいない。ここで筆者が思い出したいのは、サリー・クラインが『アフター・アガサ・クリスティー 犯罪小説を書き継ぐ女性作家たち』のなかで、『ゴーン・ガール』のことを「”最も身近な人間を本当の意味で知ることは不可能であり、限界まで追いつめられたときにどんな恐ろしい行動にでるのか想像もつかない”というテーマを見事に表現している」と評していることだ。この記述、タイトルを『少年は残酷な弓を射る』に入れ替えてもかなり当てはまるのではないだろうか。とするなら、エヴァがケヴィンによって異国を知るように、ニックがエイミーによって異国を知るという図式も成り立つのではないか。
そんなことを踏まえて注目したいのが、以下のようなニックの心の声だ。
「(前略)ここ数年、ぼくは退屈しきっていた。それは落ち着きのない子どもが訴えるような退屈さではなく(それからも卒業しきれてはいないが)、もっと重苦しい、全身を覆うような倦怠感だった。なにを見ても目新しさを覚えられずにいた。ぼくらはどうしようもないほどに徹底した非独創的社会に住んでいる(非独創的という言葉を批判的に使うこと自体が非独創的だが)。いまのぼくたちは、初めて目にするものがなにもないという、史上初の人類となった。どんな世界の驚異も無感動な冷めた目で眺めるしかない。モナ・リザ、ピラミッド、エンパイア・ステート・ビル。牙をむくジャングルの動物たちも、太古の氷山の崩壊も、火山の噴火も。なにかすごいものを目にしても、映画やテレビでは見たことがある、と思わずにはいられない。あるいはむかつくコマーシャルで。『もう見たよ』とうんざりした顔でつぶやくしかない。なにもかも見尽くしてしまっただけでなく、脳天を撃ち抜いてしまいたくなるほど最悪なのは、そういう間接的な経験のほうが決まって印象的だということだ。鮮明な映像に、絶好の眺め。カメラアングルとサウンドトラックによってかき立てられる興奮には、もはや本物のほうが太刀打ちできない。いまやぼくらは現実の人間なのかどうかさえ定かではない。テレビや映画や、いまならインターネットとともに育ったせいで、誰も彼もが似通っている。裏切られたとき、愛する者が死んだとき、言うべきセリフはすでに決まっている。色男やら切れ者やらまぬけやらを演じるためのセリフだって決まっている。誰もが同じ使い古された台本を使っている。
自動販売機で売られている無数の性格の寄せ集めではなく、リアルな本物の人間でいるというそれだけのことが、ひどく難しい時代なのだ。
そして誰もが演技しているだけだとすると、ソウルメイトなどという代物は存在しないことになる。本物の魂など持ちあわせていないのだから。
自分も他人もリアルな人間ではないわけだから、なにもかもどうでもいい。ぼくはそう思うようにさえなっていた。
リアルさをふたたび感じられるなら、どんなことでもしただろう」
エイミーが周到に仕掛けた罠にかかったニックには、確かなアリバイもなく、嫌疑がかけられる。追いつめられた彼は、若者向けのバーで飲んでいるときに、なりゆきで犯罪ブログのためのインタビューに応じる。彼のはらわたは煮えくり返っているが、それでもせいいっぱい善良な夫を演じようとする。しかし彼の発言には、真実といえるものが含まれている。
(前略)「それでいろいろ……気づかされたんだ。妻はこの世で唯一、ぼくを驚かせる力を持った相手なんだと。ほかの人間だと、言うことが予想できてしまう。みんな同じことしか言わないから。ぼくらはみんな同じ番組を見て、同じものを読んで、あらゆる情報をリサイクルしている。でもエイミーは、唯一無二の完璧な人間なんだ。そんな力を持っているのは、エイミーだけなんだ」
エイミーは最後まで、ニックが打つ手の一歩先を行く。彼は完全にからめとられるが、その立場を悲惨とはいいきれない。非独創的社会のなかで外部を喪失し、退屈しきっていた彼は、エイミーに本物の異国を見出しているからだ(ただし、『少年は残酷な弓を射る』を振り返るなら、エイミーが最後に仕掛けた罠をコントロールしきれるのかは誰にもわからない)。
サバービアは、1950年代でもグローバリゼーションの時代でもインターネットの時代でも同じように見えるが、外部の世界に対する認識は確実に変化している。欧米では、たとえばシャリ・ラペナのような(読んだことがあるのはいまのところ『The Couple Next Door』[2016]と『Someone We Know』[2019]だけだが)サバーバン・ノワールが氾濫していて、よく読まれているように見える。そうした作品では、サバービアを取り巻く外部の世界はあらかじめ失われているようにほとんど触れられないが、それでもどこかで”いま”を感じながら面白く読めるのは、このドメスティック・ノワールの系譜が炙り出すような外部の喪失がなんとなく読者に意識されているからなのではないだろうか。
《参照/引用文献》
● 『アフター・アガサ・クリスティー 犯罪小説を書き継ぐ女性作家たち』サリー・クライン 服部理佳訳(左右社、2023年)
● 『イーディスの日記(上)』『イーディスの日記(下)』パトリシア・ハイスミス 柿沼瑛子訳(河出書房新社、1992年)
● 『少年は残酷な弓を射る(上)』『少年は残酷な弓を射る(下)』ライオネル・シュライヴァー 光野多惠子・真喜志順子・堤理華訳(イースト・プレス、2012年)
● 『ゴーン・ガール(上)』『ゴーン・ガール(下)』ギリアン・フリン 中谷友紀子訳(小学館文庫、2013年)
[amazon.co.jpへ]
● 『アフター・アガサ・クリスティー 犯罪小説を書き継ぐ女性作家たち』サリー・クライン 服部理佳訳(左右社、2023年)
● 『イーディスの日記(上)』『イーディスの日記(下)』パトリシア・ハイスミス 柿沼瑛子訳(河出書房新社、1992年)
● 『少年は残酷な弓を射る(上)』『少年は残酷な弓を射る(下)』ライオネル・シュライヴァー 光野多惠子・真喜志順子・堤理華訳(イースト・プレス、2012年)
● 『ゴーン・ガール(上)』『ゴーン・ガール(下)』ギリアン・フリン 中谷友紀子訳(小学館文庫、2013年)