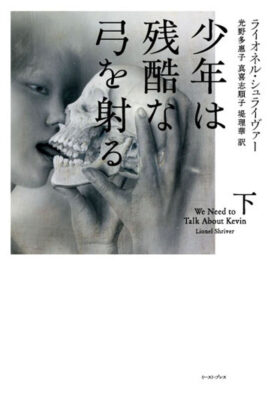そもそも日本では”ドメスティック・ノワール”というサブジャンルがまったく定着しなかったので、このようなテーマ設定についてどこから説明をはじめればよいのか悩むところだが、ドメスティック・ノワールの定義については以前の記事で何度も触れているので、そちらを参照していただければと思う(「サリー・クライン著『アフター・アガサ・クリスティー』を参照しつつ、欧米と日本における”ドメスティック・ノワール”の認知度の違いについて考える」や「現代のドメスティック・ノワールでは男女の”青ひげ”的図式が鮮やかに逆転することもある――ジュリア・クラウチ著『Her Husband’s Lover』」、「“ドメスティック・ノワール”というより”サバーバン・ノワール”と呼ぶのが相応しい舞台と男女の関係――ダーシー・ベル著『ささやかな頼み』」など)。
ここで取り上げる小説は、パトリシア・ハイスミスが1977年に発表した『イーディスの日記』とライオネル・シュライヴァーが2003年に発表した『少年は残酷な弓を射る』の2作品。それらが発表された時点では、まだドメスティック・ノワールというサブジャンルは存在しなかったので、まずはそれぞれの小説がドメスティック・ノワールとしてどう位置づけられるのかを確認しておく必要がある。参考にするのは、サリー・クラインの『アフター・アガサ・クリスティー 犯罪小説を書き継ぐ女性作家たち』だ。
ドメスティック・ノワールという呼称は、イギリスの小説家ジュリア・クラウチによって2013年に生み出され、ギリアン・フリンの『ゴーン・ガール』やルイーズ・ダウティの『Apple Tree Yard』(2013)、ポーラ・ホーキンズの『ガール・オン・ザ・トレイン』(2015)などがその代表作として成功を収め、さらに、エリザベス・ヘインズやクレア・マッキントッシュといった他の作家たちもこのサブジャンルを積極的に受け入れ、同調したことから欧米に定着した。
クラインは、このブームの源泉が、そうした作品の成功の何年も前にさかのぼり、「シャーロット・アームストロングやマーガレット・ミラー、パトリシア・ハイスミスらが書いた”マリッジスリラー”と呼ばれる小説に端を発している」と指摘している。ここで現代のドメスティック・ノワールが、パトリシア・ハイスミスにつながる。本書ではそのハイスミスの『イーディスの日記』が、以下のように紹介されている。
「『イーディスの日記』は当初、犯罪小説のジャンルには当てはまらないと見なされて出版が見送られている。だがそれは、ハイスミスが時代の先を行っていたからにほかならない。『イーディスの日記』は、一人の女性がゆっくりと、だが着実に狂気へと堕ちていく様子を描いた、暗く痛ましい不穏な物語であり、典型的なドメスティック・ノワールといえるだろう。左翼的でリベラルでもある、活動的な主婦イーディス・ハウランドは、夫とたびたび問題行動を起こす年若い息子とともにニューヨークからペンシルベニアに引っ越して以降、次第に心を病んでいく。思い描いていた完璧な新生活とは裏腹に、イーディスは家庭の退屈な骨折り仕事に追われ、夫は若い秘書の元に走り、息子はますます問題行動を起こす。だが、イーディスは日記――というよりただの妄想だが――をつけ、そこに現実とはまったく対照的な、家庭的な喜びに満ちた架空の生活を描きつづける。イーディスが思い描いた人生は家庭のあたたかさに溢れていて、夫は自分を捨てたりせずともに仲よく幸せに暮らしているし、出来損ないの息子は気立てのよい上品な女性と結婚してかわいい子どもを何人ももうけている。わたしたち女性はこれまでも日記に救われてきた」
次に、ライオネル・シュライヴァーについては、クラインの前掲書にある以下の記述が、ドメスティック・ノワールとのつながりを示している。「ルイーズ・ダウティ、ライオネル・シュライヴァー、ジュリー・マイヤーソンはその主な作品を出版社に”純文学”と見なされているが、ドメスティック・ノワールというサブジャンルに分類される小説も手がけて、大成功を収めている」。本書ではそれ以上の言及はないが、シュライヴァーの作品のなかで、この指摘に当てはまるのが、女性作家を対象とする権威ある英オレンジ賞を受賞した『少年は残酷な弓を射る』なのだ。
その内容については、のちにあらためて触れるが、とりあえず本のカバーから概要を引用しておく。「キャリアウーマンのエヴァは37歳で息子ケヴィンを授かった。手放しで喜ぶ夫に対し、なぜかわが子に愛情を感じられないエヴァ。その複雑な胸中を見透かすかのように、ケヴィンは執拗な反抗を繰り返す。父親には子供らしい無邪気さを振りまく一方、母親にだけ見せる狡猾な微笑、多発する謎の事件……そんな息子に”邪悪”の萌芽を見てとるが、エヴァの必死の警告に誰も耳を貸さない。やがて美しい少年に成長したケヴィンは、16歳を迎える3日前、全米を震撼させる事件を起こす――」
一般的には、パトリシア・ハイスミスの作品がサイコスリラーやマリッジスリラー、ライオネル・シュライヴァーの作品が純文学や主流文学に分類され、発表された年代にも隔たりがあるため、『イーディスの日記』と『少年は残酷な弓を射る』が対比されることはないが、この2作品は単にドメスティック・ノワールに分類できるだけでなく、そこには興味深い共通点がある。『少年は残酷な弓を射る』は、ケヴィンが最終的に引き起こす事件のインパクトがあるため、コロンバイン高校銃乱射事件を筆頭とするスクールシューティングとの関わりに関心が向かいがちになるが、個人的には、シュライヴァーが『イーディスの日記』にインスパイアされたのではないかとすら思えるところがある。
そこでまず2作品が扱う時代背景や小説の構成を確認しておきたい。『イーディスの日記』は、1955年から1975年にいたる時代、『少年は残酷な弓を射る』は、1980年代初頭から2001年にいたる時代を背景にしている。どちらの主人公一家もそのどこかの時点で、ニューヨークからサバービア(郊外住宅地)に転居する。ドメスティック・ノワールでは、物語が女性の主人公の目を通して主観的に描かれ、日記や手紙なども用いられるが、『イーディスの日記』では日記が、『少年は残酷な弓を射る』では手紙が、主人公の複雑な内面を炙り出すのに重要な役割を果たしている。
『イーディスの日記』の物語は、1955年、主人公イーディス・ハウランドと夫のブレット、10歳になった息子のクリッフィー、ペットの猫ミルデューが、ニューヨークのグローヴ・ストリートからペンシルバニア州にあるサバービア、ブランズウィック・コーナーに引っ越すところからはじまる。イーディスは、地方の新聞社に移ったブレットとともに、若干左寄りの健全なアメリカのリベラリズムを代表するような新しい新聞を発行しようと考えていた。
しかし彼女は、長年求めつづけてきたはずのサバービアの生活のなかで、次第に意気消沈し、憂鬱から抜け出せなくなる。息子のクリッフィーは、無気力で進路が定まらず、問題行動を繰り返す。大学の入学試験ではカンニングが露見し、両親を落胆させる。その後、バーテンダーとして働くようになるが、麻薬をさばいたりもする友人とつるみ、バーで喧嘩して警察沙汰になったり、運転する車で人をはねて負傷させる事故を起こす。
悩みはそれだけではない。一家は、引っ越して間もなく年老いたブレットの伯父ジョージを引き取る。背中が悪いというジョージは、トイレに起きる程度のことはできたが、やがて寝たきりになり、イーディスの負担が増えていく。クリッフィーは、自分が使うはずだった部屋をジョージに占領されたことから、老人を嫌い、苛立ちをぶつけるようになる。
それに追い打ちをかけるのが、ブレットの裏切りだ。ブレットは不倫していた若い秘書キャロルに本気になり、イーディスに別居、離婚を切り出す。彼は家を離れ、ニューヨークに戻ってキャロルと暮らし、やがて再婚し、子供も生まれる。イーディスの心の支えは、ときどき訪ねてくる大伯母メラニーだけだったが、彼女は脳卒中の発作を起こし、帰らぬ人になる。
イーディスは大学生のときに知人の男性からプレゼントされたぶ厚い日記帳に印象に残ったことをつづってきたが、クリッフィーが入試に失敗したころから嘘を書いて憂鬱を晴らすようになる。その内容は、現実に絶望するほど妄想がエスカレートしていく。日記の世界では、クリッフィーこそが希望の星になっている。彼は大学を卒業し、技術者として就職し、良家の娘デビーと結婚し、仕事でクウェートに赴任する。やがてイーディスのなかでは、現実と妄想の境界が揺らいでいく。
一方、シュライヴァーの『少年は残酷な弓を射る』については、まずその独特な構成に触れておくべきだろう。物語の背景になるのは、先述したように1980年代初頭から2001年にいたる時代だが、物語が始まるのは2000年11月。主人公エヴァ・カチャドリアンの息子ケヴィンが社会を震撼させる事件を起こすのが1999年4月なので、すでに事件が起こり、その後から物語がはじまる。しかもその物語は、2000年11月から2001年4月にかけて、エヴァが夫のフランクリンに宛ててつづった手紙だけで構成されている。そのフランクリンがどこでどうしているのかは、終盤になるまで明らかにされない。
それらの手紙では現在と過去が複雑に入り組んでいるが、エヴァと家族の設定を整理すると以下のようになる。エヴァとフランクリンは1970年代後半に出会い、子どもを持つことを考えるようになったころにはニューヨークのトライベッカにあるアパートに暮らしていた。エヴァは、かつてわずかな現金を持ってはじめてヨーロッパに出かけたときに思いついたガイドブックが当たり、人気の旅行ガイドシリーズを手がける会社を経営し、世界を飛び回る生活を送っていた。フランクリンは、広告代理店のロケーションマネージャーだった。
エヴァは子どもがほしくなかった。子どもを持つこと、母親になることを心底恐れていた。赤ん坊が自分の嫌なところをすべて暴くかもしれないとも思った。しかし彼女はフランクリンを深く愛していて、彼が求めたわずかなもの、彼女に提供できるものが子どもだった。息子のケヴィンが生まれたのが1983年で、親子は息子が3、4歳になるころに、トライベッカからハドソン川対岸、ニューヨーク州ロックランド郡にある最近になってできたサバービア、グラッドストンに転居する。そこでケヴィンの妹シーリアが生まれ、4人家族になる。
母親となったエヴァは、ケヴィンがまだ赤ん坊のころから翻弄される。ふてくされた表情はすでに1歳のときにあった。最初は母乳を嫌がると思っていたが、温めた粉ミルクでも、フランクリンが飲ませないと受けつけないことから、母乳ではなく母親を嫌がっているのがわかる。何ヵ月も前にしゃべれるようになっていたのに、それを隠して、親の会話を盗み聞きしていたのではないかと思える。6歳までおむつがとれなかったのも故意で、便を小出しにしていたように思える。
成長するケヴィンの周囲では、奇妙な事件が頻発する。幼稚園では、全身に湿疹があり、肌に触れるのを我慢していた女の子が、突然、解放されたように肌をかきむしって騒ぎになる。親しくしていた隣人の息子が、自転車の不具合で大怪我をする。ケヴィンとふたりで留守番をしていた妹のシーリアが、排水管洗浄剤を顔に浴び、片目を失ってしまう。学校の英語教師が、ケヴィンの証言でセクハラの濡れ衣を着せられる。エヴァはそのたびケヴィンがいかに危険であるのかをフランクリンに訴えるが、父親の前ではケヴィンが行儀よくしているため、彼には母親が息子に対して冷淡であるようにしか見えない。
そこで注目したいのが、エヴァがケヴィンという存在をどのように感じているかということだ。印象的な記述をふたつ抜きだしてみたい。
「『ケヴィン、いい? ケヴィンはなにが好き?』
これはケヴィンには答えることができない質問だった。ちなみに彼は17歳になったいまでも、この問いに対してわたしを満足させる答えはおろか、自分を満足させるような答えさえ見つけられないでいる」
(これは事件後、フランクリンの両親に対するエヴァの発言)「(前略)わたしはなんとかケヴィンを罰しようとして、この16年間のほとんどをそれに費やしてきました。でも、まず、あの子からなにを取りあげてもあの子は平気なんです。屈辱を味わわせることもむり。辱められても、良心のある人間でなければ苦しむことはありません。罰することができるのは、絶たれたら困る希望を持っている人、切られたくない絆のある人、ほかの人が自分をどう思っているかを気にかける人だけなんです。罰するためには、その人が多少なりとも善なる部分を持っていなくてはだめなんです」
では、こうした記述を踏まえて『イーディスの日記』で、イーディスがクリッフィーのことをどう思っているかを振り返ってみたい。
「彼女に悩みがあるとすれば、それはクリッフィーのことにほかならなかった。息子が学校でうまくいっていないのはわかっていた。努力をしないし、自らリーダーシップを取ろうともしない。一番好きなことといえば、テレビの前に座っていることぐらい、それも別に見ているわけではなく、ただうつらうつらしたり、爪を噛んだりしているだけだった。だがそれ以上に深刻なのは、同年代の子供たちと友達になれないことだった。彼は何事に対しても、誰に対しても、積極的に自分から好きになるということがなかった」
無気力なクリッフィーを心配したイーディスは、夫のブレットに息子と話をするように説得する。ブレットは息子をキャンプ旅行に連れだし、一泊して戻ってくる。その晩、夫婦のあいだでこんな会話が繰り広げられる。
「『今朝目を覚ましたら、あいつが銃を構えて見おろしていたんだ』とブレットはいった。
『おかしいだろ?』
銃? 22口径ウィンチェスターのことだ、とイーディスは思った。クリッフィーがそれを構えている姿が容易に想像できた――しかも薄笑いを浮かべて。
『冗談に決まってるわ』
『さあな』ブレットはバスローブを脱ぎ捨てた。『とにかくぞっとした気分だったよ。もちろん笑おうとしたさ。でもあいつの指は引き金にかかっていたんだぞ!』一階の奥の部屋にいるクリッフィーに聞こえるとでもいうように、ブレットは声をひそめてしゃべっていた。突然、彼は笑い出した。『まあ、ともかく無事に生きているがね』
本当にそんなことがあったのだろうか。たぶん本当のことなのだろう――ブレットの言葉もクリッフィーの行動も、銃の――あの軽い銃は近距離なら簡単に人が殺せる――ことも。ブレットが息子と人生について真剣な話をしたかどうかはわからなかった。だが聞くのははばかられた」
以下はペットのミルデューがベッドにもぐり込んできたときのこと。「突然イーディスはあることを思い出して慄然とした――ニューヨーク最後の日のことを、クリッフィーがミルデューを布団むしにして窒息させようとしたあげく、もう少しで成功しかけたときのことを。ああ、なんて恐ろしいことだろう」
クリッフィーの行動は、ケヴィンほど邪悪で狡猾ではないが、それぞれの母親が息子に感じていることには通じ合うものがある。
2作品の共通点はそれだけではない。次に注目したいのは、サバービアの閉塞感のなかで、主人公たちの外部の世界に対する認識がどのように変化していくかということだ。
イーディスにとって最良の思い出は外部の世界と結びついている。「イーディスの脳裏に、17歳の夏メラニー伯母さんとヨーロッパ旅行をした思い出がよみがえった。クイーン・メリー号のファーストクラスで二人はサウザンプトンに向かい、それからロンドン、パリ、ローマ、フィレンツェ、ヴェニスと旅して回ったのだ。それはイーディスの人生で最高の二ヵ月だった。そのときの記憶は今でも鮮やかな美しさをもって生き生きと呼び起こすことができる。そのときの旅の詳細を――たとえばフィレンツェで見た、雨に濡れるミケランジェロのダビデ像――を彼女はあとになって日記に書きつづった」
では、日記の内容が妄想に切り替わったあとにも外部はあらわれるのか。興味深いのは、現実とは違って希望の星となったクリッフィーの活躍と外部が結びついていることだろう。
「今やクリッフィーは一週間に一度、仕事のためにニューヨークへ出かけ、デビーと共同で借りているアパートメントで一泊していった。二ヵ月に一度、彼は会議のためにアメリカに帰り、同じ会社のエンジニアたちと(たった今飛び立ってきたばかりの)クウェートで現在彼が手がけている仕事について話し合い、あるいはニュージャージーの我が家にこもり、秘密の発明――会社を除けば誰にも、妻のデビーにさえも打ち明けようとしなかった――に打ち込んでいた」
イーディスのなかで、外部が息子の存在と結びつくことを踏まえ、今度は、エヴァの外部の世界に対する認識を確認したい。彼女の場合は、仕事で旅行ガイドを手がけているだけに、その認識の変化も際立っている。彼女は、子どもを持つことを考えはじめたとき、外部の世界について以下のように考える。
「(前略)わたしは旅を続けるうちに、たとえばモロッコに行って家に入るときに靴を脱ぐことになっているのかどうかを気にするより、なるほど、どの国にも靴に関する習慣があるんだなと、そちらに関心が行くようになったの。そう思いはじめると、気候も建物もげっぷや靴に関する習慣もどこにでもあるものだから、わざわざ手荷物を預けたり、時差に慣れたりしながら、苦労してどこかへ行っても、また同じところに到着したようにしか思えなくなってしまった。世界が均一化しているということに関しては、わたしもしょちゅうグローバリゼーションに文句をいっているけど――あなたがいつも履いていた焦げ茶のストーブパイプ型の作業靴だって、いまやバンコクのバナナ・リパブリックでも買えるのよ――、ほんとうに均一化してしまったのはわたしの頭のなかにある世界、つまり世界のことをわたしがどう考えるか、どう感じるか、どう語るか、だったんだわ。だから、ほんとうの意味でどこかちがう場所へ行こうと思ったら、もうちがう空港に降りたつのではだめ。ちがう人生、ちがう生活に旅をしなければならないのよ。
『母親になるという体験が――』と、わたしはあなたにいった。『新しい国なのよ』」
これはエヴァが母親になる以前の発言で、参考にはなるが、すべてを経験したあとの結論ではない。その後、ケヴィンが生まれ、サバービアに転居することを望むフランクリンとニューヨークが大好きなエヴァが対立したとき、彼は以下のように妻をたしなめる。「きみはいまだにわかってないみたいだね。もしかしたら、母親になることを『べつの国』になぞらえたあたりがまちがいのもとだったのかもしれない。子どもを育てるということは外国に観光旅行に行くのとはちがうんだ。ケヴィンがエレベーターのドアにはさまれて手を失ったら、きみはどんな気がすると思う? こんな空気の悪いところにいて喘息にでもなったら? きみがスーパーで買い物をしているあいだに、誘拐でもされたら?」
エヴァ自身もこの時点では、母親になることに、新しい国やべつの国を見出してはいない。だから彼女は、サバービアへの転居を受け入れるのと引き換えに、旅行ガイドの新たな企画のためにアフリカに旅立つ。そして、外部の世界を体験することで心境が変化する。
「(前略)アフリカには20代のときに一度来たことがあって、そのときはものすごく感動したのよ。あのときのアフリカはほんとに別世界だった。その後、野生動物は激減し、逆に人口は爆発的に増え、そういうことからくる貧困は驚くほど進んでいた。プロの目でこのときにまわった国を査定すると、すべて問題外だった(後略)」
「この旅行は、はじめてわたしが冒険心からではなく計画したものだった。自分がまだ若くて好奇心にあふれ、まだ自由であることを証明したくて、つまり自分が変わっていないことを証明したくて、出かけてきた旅行だった。でも、終わってみたら結局、わたしの生活が以前とはちがうということを思いしらされただけだった。自分が42歳という年齢相応にもう若くはないこともわかった(後略)」
「(前略)わたしの育児体験はまだまだ片足のつま先を水面にちょっとつけただけにすぎないという結論に達した。1982年には紆余曲折のすえに子どもを産むという決意をしたわけだけど、その決意をあらたにして、両足で育児の世界に飛び込まなければと思った。もう一度ケヴィンを産みなおそうと思った。わたしがそれに抵抗さえしなければ、出産と同じように子どもを育てることでも、世界が変わるような体験ができるはずだから」
そんな決意によってエヴァは、想像を絶する体験をすることになる。その結果はやはり、外部やべつの国と結びつけて表現される。「これと同じような無邪気さで、若いころのわたしも行動してたんだわ――スペインにも木が生えていたといっては落胆し、どんな辺境に行ってもそれなりの食べ物や気候があると知ってはがっかりしていた。わたしはどこかまったく違う世界へ行きたかった。異国を求めることにかけては、わたしの情熱は尽きることがないんだと、愚かにも思いこんでいた。
わたしはケヴィンによって本物の異国を知ったわ。それはまちがいない。だって、異国って、なにがなんでもわが家に帰りたいという焼けつくような願望を抱かせる場所だから」
筆者には、イーディスもエヴァも、かつて確かなものであった外部の世界を喪失し、息子のなかにそれに代わるものを見出しているように思える。そんなふうに感じるのは、2作品にもうひとつ、見逃しがたい共通点があるからだ。
どちらも母親と息子のあいだには越えがたい深い溝があるように見えるが、物語の最後に見えない絆で結ばれていることを示唆するエピソードが盛り込まれている。
イーディスが最後にどうなるのか、ここでは触れないが、クリッフィーは彼女のぶ厚い日記を回収する。その日記に畏敬の念を抱き、決してそれを開くことなく、クローゼットの隅に隠し、死ぬまで守りつづけようと心に誓う。一方、エヴァは事件から二周年目の記念日に、少年刑務所に収監されているケヴィンと面会する。彼は母親に、作業室でつくったらしい棺のような形の箱を差し出し、決して開けないように念を押す。エヴァには中身がなんだかわかる。ケヴィンは刑務所のなかではそれを守れないと思い、彼女に委ねるのだ。
この日記や箱を媒介とした母親と息子のつながりは、深く共鳴している。やはりシュライヴァーは、『イーディスの日記』にインスパイアされたように思えてならない。
《参照/引用文献》
● 『アフター・アガサ・クリスティー 犯罪小説を書き継ぐ女性作家たち』サリー・クライン 服部理佳訳(左右社、2023年)
● 『イーディスの日記(上)』『イーディスの日記(下)』パトリシア・ハイスミス 柿沼瑛子訳(河出書房新社、1992年)
● 『少年は残酷な弓を射る(上)』『少年は残酷な弓を射る(下)』ライオネル・シュライヴァー 光野多惠子・真喜志順子・堤理華訳(イースト・プレス、2012年)
[amazon.co.jpへ]
● 『アフター・アガサ・クリスティー 犯罪小説を書き継ぐ女性作家たち』サリー・クライン 服部理佳訳(左右社、2023年)
● 『イーディスの日記(上)』『イーディスの日記(下)』パトリシア・ハイスミス 柿沼瑛子訳(河出書房新社、1992年)
● 『少年は残酷な弓を射る(上)』『少年は残酷な弓を射る(下)』ライオネル・シュライヴァー 光野多惠子・真喜志順子・堤理華訳(イースト・プレス、2012年)