犯罪小説のサブジャンルとして欧米に定着した”ドメスティック・ノワール”という呼称を生み出したのが、イギリスの小説家ジュリア・クラウチであることは、前の記事「サリー・クライン著『アフター・アガサ・クリスティー』を参照しつつ、欧米と日本における”ドメスティック・ノワール”の認知度の違いについて考える」に書いた。このサブジャンルの特徴については、そちらを参照していただければと思う。
2011年に『Cuckoo』でデビューしたクラウチは、A・J・アーリッジとの合作を含め10本の長編を発表し、「ドメスティック・ノワールの女王」とも呼ばれているが、邦訳はされていない。ここで取り上げる5作目の『Her Husband’s Lover』(2017)は、彼女の代表作のひとつといっていいだろう。アガサ・クリスティーから女性作家による犯罪小説の系譜をたどったサリー・クラインの『アフター・アガサ・クリスティー 犯罪小説を書き継ぐ女性作家たち』では、この小説が以下のように紹介されている。
「傑出したドメスティック・ノワールのスリラーはほかにもある。そのひとつが、ジュリア・クラウチの『Her Husband’s Lover』(2017)だ。この作品は、交通事故で夫と子どもを失ったルイーザ・ウィリアムズと、ルイーザに残されたものをすべて奪おうとする、夫の子を身ごもった情緒不安定な愛人ソフィーの二人が繰り広げる暗澹とした不穏な物語である」
『Her Husband’s Lover』の物語は、緊迫したカーチェイスからはじまる。主人公のひとり、ルイーザ・ウィリアムズは、ふたりの子どもを自分のフィエスタに乗せて必死に逃げている。そんな母子に迫るのは、ルイーザの夫サムが運転するポルシェだ。彼女のフィエスタは追いついたポルシェにはじかれて道を逸れ、オークの木に衝突し、ポルシェも追突する。この事故でサムと子どもたちは死亡し、ルイーザだけが九死に一生を得る。
事故から5か月後、まだむち打ちの後遺症に悩まされるルイーザは、検死法廷で唯一の証人として証言することになる。現場に残されたタイヤ痕は、サムがルイーザの車を道からはじき出し木に激突させたことを示していた。ルイーザの医療記録は、彼女を苦しめてきた家庭内の虐待の歴史を物語っていた。さらに、サムの書斎からは、数年前に遺体で発見された彼の最初の妻ケイティの死に、彼が関わっていたことを示す証拠も発見された。証言台に立ったルイーザは、サムから、別れようとすれば死ぬまで追いつめると脅されていたと証言する。そのとき、サムの愛人だったソフィーが傍聴席から立ちあがり、彼女は嘘つきだ、彼ははめられた、家族を助けようとしていたと訴える。だが、薬物乱用の過去があり、司法妨害や薬物所持で服役もし、事件以来、悪意のあるソーシャルメディア・キャンペーンを行っていた彼女は、すぐに法廷から締め出される。
本作は、引用したサリー・クラインの記述にもあるように、夫と子どもを亡くしたルイーザと夫の子を身ごもった愛人ソフィーのふたりを軸に展開していく。ルイーザはブリストルでデザイナーとして活躍していたが、デジタル市場で成功した実業家サムに出会い、結婚して、ケンブリッジシャーの田舎に建つ豪邸に引っ越した。ふたりの子どもにも恵まれたが、サムからの虐待によって関係は悪化し、結婚生活は悲惨な結末を迎えた。莫大な遺産を相続したルイーザは、豪邸の売却を決め、ロンドン中心部にあるプールやジムを備えた高層住宅に移り、デザイン会社に迎えられ、デザイナーとして新たなスタートを切る。一方、ソフィーは、ルイーザの配慮によって、サムの経済的支援で暮らしていたケンブリッジのアパートに、お腹の子が生後6か月になるまで留まることを許されたが、ルイーザに接触することは禁じられた。自分と子どものものであるはずの遺産をルイーザに奪われたと考えるソフィーは、あらゆる手段を使ってルイーザの化けの皮を剥がし、すべてを取り戻そうと画策する。
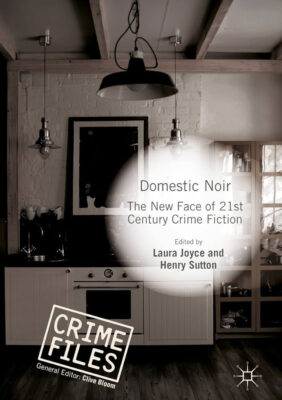
『Domestic Noir:The New Face of 21st Century Crime Fiction』edited by Laura Joyce & Henry Sutton (Palgrave Macmillan, 2018)
本作の設定や登場人物がある程度見えてきたところで振り返っておきたいのが、イギリスのイースト・アングリア大学でクリエイティブ・ライティングの講師を務めるローラ・ジョイスとヘンリー・サットンが編集したドメスティック・ノワールの研究書『Domestic Noir: The New Face of 21st Century Crime Fiction』だ。前の記事でも触れたように、その序文は、このサブジャンルの呼称の生みの親であるジュリア・クラウチが書いている。そのなかで彼女は、現代のドメスティック・ノワールとそれ以前との違いにも言及している。クラウチがドメスティック・ノワールという造語を生み出したのは2013年のことだが、その源流として、たとえば、シャーロット・アームストロングやマーガレット・ミラー、パトリシア・ハイスミスらが書いた”マリッジスリラー”が認知されている。クラウチが指摘しているのは、そうした源流となる作品と現代のドメスティック・ノワールの違いだ。
「現代のドメスティック・ノワールが違うのは、小説の中心に位置する女性たちが、単に被害者になるだけでなく、場合によっては加害者にもなることです。彼女たちには欠陥があり、傷つき、出来事に打ちのめされることもあれば、勝利を収めることもあります。重要なのは、物語が女性の主人公の目を通して主観的に描かれている点です」
このクラウチの指摘は、本作にも当てはまる。ルイーズとソフィーの図式は明確なように見えるが、彼女たちの言動や行動には「信頼できない語り手」の性格が見え隠れし、それぞれの印象が変わり、被害者と加害者の境界が曖昧になっていく。
ルイーズは、デザイン会社では過去を完全に封印し、ルー・ターナーを名乗り、ニューヨーク出身で、ふたりの子どもを育てる母親でもあるという別人を演じる。物語のなかで彼女の過去が次第に明らかになると、結婚生活の印象も変わる。彼女は産後うつ病になり、サムの浮気をかぎつけると、ある行動に出る。その目的が見えてくると、ギリアン・フリンの『ゴーン・ガール』のエイミーが脳裏をよぎったりもする。
一方、ソフィーには、薬物乱用や司法妨害など悪い印象しかないが、その背景からは別の物語が見えてくる。15歳でスカウトされ、モデルとしてキャリアをスタートさせた彼女は、羊の皮を被った狼のような有名カメラマンの餌食になり、どん底に突き落とされた。彼女はレイプや薬物から負のスパイラルに陥り、服役することになった。
しかし本作にはもうひとり、重要な役割を果たす人物が登場する。若い映像作家アダムだ。ルイーズが移った高層住宅の目の前の土地では、再開発事業が進められ、アダムは再開発を題材にしたドキュメンタリーを撮影していた。そんなアダムが構えるカメラの視野にルイーズが入ったことからふたりは出会い、惹かれ合い、料理好きのアダムがルイーズのアパートメントに入り浸るようになる。
そこで思い出したいのが、「青ひげ」の物語だ。ドメスティック・ノワールの小説では、「青ひげ」がモチーフになっていることが少なくないが、本作ではそれが大きな効果を生み出している。まず注目したいのは、ルイーズとサムの関係だ。以前、サムにはケイティという妻がいたが、その妻の死に彼が関わっていることを示す証拠が見つかる。そして、サムのもとから逃げようとしたルイーズも、彼に殺されそうになった。そこには「青ひげ」のモチーフが意識されている。
それを踏まえると、ルイーズとアダムの関係がより興味深くなる。ルイーズはアダムに自分のことをほとんど語ろうとしない。彼女のアパートメントには、アダムが入れない開かずの間がある。その開かずの間にすべての答えがあるわけではないが、アダムが彼女の住居で少しずつ秘密を解き明かすうちに、ルイーズが自分が思っているような人物とは違うことに徐々に気づいていく。そのとき男女の「青ひげ」的な図式が逆転していくことになる。
さらに、ルイーズとアダムの関係には、別な意味でも皮肉が込められている。アダムはドキュメンタリー作家であり、そんな視点で彼女をとらえていたはずが、実体ではなく虚構の産物を見させられているのかもしれない。そしてもうひとつ、アダムは、再開発によって住み慣れた場所を奪われる人々の立場から、ジェントリフィケーションを批判的にとらえている。一方、ルイーズは、再開発によってすぐ目の前に富裕層向けの豪華な高層ビルが建つことを知ると、その最上階に住むことを真剣に考えるようになる。弱者の立場に立っていたアダムは、気づかぬうちにそんなルイーズのヴィジョンに引きずり込まれかけている。
クラウチは、単に「青ひげ」的な図式を逆転させるだけでなく、そこにジェントリフィケーションの問題も反映することで、男女の力関係の変化や男女の間にある深い溝を際立たせている。
《参照/引用文献》
● 『アフター・アガサ・クリスティー 犯罪小説を書き継ぐ女性作家たち』サリー・クライン 服部理佳訳(左右社、2023年)
● 『Her Husband’s Lover』Julia Crouch (Headline Book Publishing, 2017)
● 『Domestic Noir: The New Face of 21st Century Crime Fiction』edited by Laura Joyce & Henry Sutton (Palgrave Macmillan, 2018)
[amazon.co.jpへ]
● 『アフター・アガサ・クリスティー 犯罪小説を書き継ぐ女性作家たち』サリー・クライン 服部理佳訳(左右社、2023年)
● 『Her Husband’s Lover』Julia Crouch (Headline Book Publishing, 2017)
● 『Domestic Noir: The New Face of 21st Century Crime Fiction』edited by Laura Joyce & Henry Sutton (Palgrave Macmillan, 2018)
● 『ゴーン・ガール(上)』『ゴーン・ガール(下)』ギリアン・フリン 中谷友紀子訳(小学館文庫、2013年)

