ダーシー・ベルの長編デビュー作『ささやかな頼み』については、まず裏表紙の紹介文を引用しておくべきだろう。
「シングルマザーのステファニーは同じ幼稚園に子どもを通わせているエミリーと友人になる。だがある日、エミリーはステファニーに息子を預けたまま引き取りに現れず、失踪してしまった。順風満帆な人生を送っていたはずの彼女にいったい何が? ステファニーは自らが運営する育児ブログで情報提供を呼びかけるが……。女たちの友情の裏に渦巻く悪意の全貌とは。英米ミステリ界を席巻するドメスティック・ノワールの真骨頂」
まず注目したいのは、「英米ミステリ界を席巻するドメスティック・ノワールの真骨頂」という謳い文句だ。これはハリエット・タイスの『紅いオレンジ』の裏表紙にある謳い文句とは対照的だ。前の前の記事「ほんのわずかな時間ではあってもヒロインが独力で”青ひげ”と対峙することが意味を持つドメスティック・ノワール――ハリエット・タイス著『紅いオレンジ』」で書いたように、『紅いオレンジ』は欧米ではドメスティック・ノワールとして評価されていたが、日本ではこのサブジャンルがまったく定着しなかったので、それを使うのを避け、裏表紙の謳い文句は「戦慄のリーガル・スリラー」というように既成のサブジャンルで埋め合わせていた。その結果、”リーガル・スリラー”という謳い文句に違和感を覚えるといった感想も見られた。
それを踏まえるなら、『ささやかな頼み』で”ドメスティック・ノワール”を前面に出しているのはよいことのように見える。だが問題は小説の中身だ。これは本当に「ドメスティック・ノワールの真骨頂」といってよいのだろうか。
すでに何度も書いているように、ドメスティック・ノワールというサブジャンルは、2013年にイギリスの小説家ジュリア・クラウチによって生み出された。彼女のホームページではそれが以下のように説明されている。ドメスティック・ノワールは主に家庭や職場を舞台にし、主に女性の経験に焦点を当て、人間関係を軸に据え、家庭という空間はそこに住む人々にとって困難で、時に危険な場所にもなりうるという、広くフェミニズム的な視点に基づいている。
この基本的な説明を、さらにふたつの資料で補足しておきたい。まず、サリー・クラインは、アガサ・クリスティーの登場から現代にいたるまで、女性作家による犯罪小説の系譜をたどった『アフター・アガサ・クリスティー 犯罪小説を書き継ぐ女性作家たち』のなかで、このサブジャンルを以下のように説明している。
「(前略)懐の深いこのジャンルは写実小説の一形式で、精神疾患の虚像と現実、家庭と職場における女性の権利、リベラル・フェミニズムとラディカル・フェミニズム、宗教、家族、母性、家庭内暴力といった、まったく異なる思想や理想をすべて扱う。こうした小説は、家庭は聖域であるという考えを覆している。多くの女性にとって家庭はその対極にある。家庭は檻であり、精神的、心理的に虐げられる場だ。成長も、ときには息をつくことすらもできない場所なのである」
この説明だと女性がみな被害者のような印象を与えかねないので、もうひとつの資料にも注目しておく。
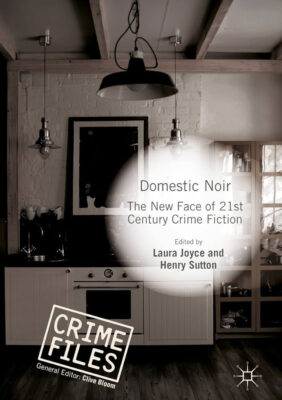
『Domestic Noir:The New Face of 21st Century Crime Fiction』edited by Laura Joyce & Henry Sutton (Palgrave Macmillan, 2018)
イギリスのイースト・アングリア大学でクリエイティブ・ライティングの講師を務めるローラ・ジョイスとヘンリー・サットンが編集したドメスティック・ノワールの研究書『Domestic Noir: The New Face of 21st Century Crime Fiction』だ。序文を書いているのはジュリア・クラウチ。そのなかで彼女は、現代のドメスティック・ノワールとそれ以前との違いにも言及している。先述したようにドメスティック・ノワールという造語が生まれたのは2013年だが、その源流として、たとえば、シャーロット・アームストロングやマーガレット・ミラー、パトリシア・ハイスミスらが書いた”マリッジスリラー”が認知されている。クラウチが指摘しているのは、そうした源流となる作品と現代のドメスティック・ノワールの違いだ。
「現代のドメスティック・ノワールが違うのは、小説の中心に位置する女性たちが、単に被害者になるだけでなく、場合によっては加害者にもなることです。彼女たちには欠陥があり、傷つき、出来事に打ちのめされることもあれば、勝利を収めることもあります。重要なのは、物語が女性の主人公の目を通して主観的に描かれている点です」
こうした定義に当てはまる作品として、ギリアン・フリンの『ゴーン・ガール』(2012)やルイーズ・ダウティの『Apple Tree Yard』(2013)、リアーン・モリアーティの『ささやかで大きな嘘』(2014)、ポーラ・ホーキンズの『ガール・オン・ザ・トレイン』(2015)などが、ドメスティック・ノワールの代表的な作品とされている。
それでは、ダーシー・ベルの『ささやかな頼み』の場合はどうか。確かに、女性の主人公の目を通して主観的に描かれてはいる。だが、ふたりの主人公、ステファニーにとっても、エミリーにとっても、家庭は檻ではないし、精神的に虐げられる場でもない。上に挙げた代表的な作品では、それが男性優位であれ、裏切りや暴力、ガスライティングであれ、男性の登場人物とのあいだに、さまざまなレベルでのせめぎ合いがある。しかし本作では、すでに事故死しているステファニーの亡夫デイヴィスにも、エミリーの夫ショーンにも”青ひげ”的な要素は皆無であり、どちらもはなから被害者といってもいい。だから、男女の関係を通して家庭が困難で危険な場となることがあるとすれば、原因は単に彼女たちにある。彼女たちがそれぞれに抱え込んでいる秘密が危険なのであり、自己の欲望に忠実で身勝手な彼女たちの存在そのものが、家庭を危険にさらすのだ。
本作は、ドメスティック・ノワールというよりも、サバーバン・ノワールと呼ぶべきだと思う(このサブジャンルの呼称もそれなりに流通している)。サバービア(郊外住宅地)を舞台に、幸せそうに見える家族がそれぞれに秘密を抱えていて、そこから犯罪や混乱が巻き起こるようなノワールだ。たとえば、カナダの小説家シャリ・ラペナの『The Couple Next Door』(2016)や『Someone We Know』(2019)などはその典型だろう。そんなサブジャンルをわざわざ引っ張りだすことに意味があるのかと思われるかもしれないが、ドメスティック・ノワールが定着した欧米では(サリー・クラインは前掲書で「飽和状態」と表現してもいる)、サバービアを舞台に家族と犯罪が描かれればドメスティック・ノワールになりかねない印象もあり、一線を引くためにサバーバン・ノワールというサブジャンルは有効だと思える。そちらにはそちらならではの面白さがあるからだ。
『ささやかな頼み』では、コネチカット州のウォーフィールドというサバービアに暮らすステファニーとエミリーが1年ほど前に親しくなったことが後々ひとつのポイントになってくるが、その出会いはサバービアと無関係ではない。そこでまず、ステファニーとサバービアとの関わりが見える記述を抜きだしてみたい。以下は彼女のブログの一部だ。
「でも、コネチカットのママたちとは全然ウマが合わなかったの。全員が強い仲間意識で結ばれ、よそ者を寄せつけないその姿は、中学校時代の意地悪な女の子に戻ったかのようだった。わたしが話しかけようとすると、互いに顔を見合わせ、みんなして目をぐるりとまわすんだもの。礼儀としていちおうわたしのことは見ても、すぐに自分たちだけで話しはじめるのが常だった。
ブログを始めたのはそれが理由――(中略)わたしが自信喪失を克服できたのは、友だちがいなくて孤独だと感じているママは自分ひとりじゃないと気づけたからなの」
「母は父の死からほどなく亡くなった。わたしは母のようになるのがいやだった。失意のうちに死ぬなんて。当時、胸をひらいて話せる相手はひとりもいなかった。街に住んでいたときの友人たちは着々と自分の人生を歩んでいたから、結婚して子どもを産んだわたしを――説得に応じて郊外に引っ越したわたしを見下している気がしてしょうがなかったの。
夫と兄が事故で死んだことはこの町の人全員に知れ渡っていた。玄関に置かれた差し入れのキャセロールやサンドイッチ、ケーキを全部食べていたら、確実に五十ポンドは太ったと思う。でも、しばらくすると一種のリバウンドが始まった。悲劇がうつるとばかりに、誰もがわたしを避けるようになったわ」
そんな孤独なステファニーに声をかけたのがエミリーで、ふたりは親しくなった。エミリーがステファニーに接近した本当の目的は後半のほうで明らかにされる。そんな関係がポイントになることを踏まえると、やはりサバーバン・ノワールのほうが相応しい。日本では、ドメスティック・ノワールが定着しなかったうえに、本書の「ドメスティック・ノワールの真骨頂」を真に受けると、このサブジャンルのイメージが歪んでしまうように思える。
《参照/引用文献》
● 『ささやかな頼み』ダーシー・ベル 東野さやか訳(早川書房、2017年)
● “Genre Bender” by Julia Crouch (Blog / August 25, 2013)
● 『アフター・アガサ・クリスティー 犯罪小説を書き継ぐ女性作家たち』サリー・クライン 服部理佳訳(左右社、2023年)
● 『Domestic Noir: The New Face of 21st Century Crime Fiction』edited by Laura Joyce & Henry Sutton (Palgrave Macmillan, 2018)
[amazon.co.jpへ]
● 『ささやかな頼み』ダーシー・ベル 東野さやか訳(早川書房、2017年)
● 『アフター・アガサ・クリスティー 犯罪小説を書き継ぐ女性作家たち』サリー・クライン 服部理佳訳(左右社、2023年)
● 『Domestic Noir: The New Face of 21st Century Crime Fiction』edited by Laura Joyce & Henry Sutton (Palgrave Macmillan, 2018)

