SJ・ワトソンの長編デビュー作『わたしが眠りにつく前に』は、ドメスティック・ノワールというサブジャンルが定着した欧米では、いまではそれを代表する作品として認知されている。いまではと書いたのは、当初はそのように評価されなかったということではない。ワトソンが本作を発表した2011年には、ドメスティック・ノワールという呼称はまだ生まれていなかった。
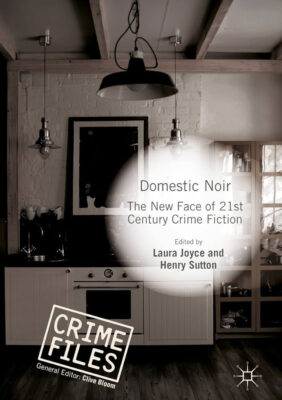
『Domestic Noir:The New Face of 21st Century Crime Fiction』edited by Laura Joyce & Henry Sutton (Palgrave Macmillan, 2018)
ドメスティック・ノワールを取り上げるたびに書いているように、この呼称は、ワトソンと同じイギリスの小説家ジュリア・クラウチによって2013年に生み出された。ドメスティック・ノワールの研究書『Domestic Noir: The New Face of 21st Century Crime Fiction』に収められたクラウチの序文を読むと、クラウチとSJ・ワトソンにはデビュー当時ちょっとした縁があったことがわかる。その部分を抜きだして簡単にまとめると以下のような話になる。
クラウチのデビュー作『Cuckoo』が出版社に受け入れられた2009年には、ソフィー・ハナが人気急上昇中で、『Little Face』が出版されたばかりで、”カルヴァー・ヴァレー”シリーズが読者に強い印象を残していた。クラウチも夢中になって読み耽り、警察は登場するものの、女性の家庭における体験、密室で起こる出来事に焦点をあてているところに興味を覚えていた。出版業界はその手のサイコロジカル・スリラーを渇望していたため、クラウチがあるイベントに出席したとき、広報担当者が、クラウチと『わたしが眠りにつく前に』でデビューするSJ・ワトソンを含む5人の新人作家を図書館の司書たちに「新しいソフィー・ハナ」と紹介するほどだったという。そんなわけで、彼女のデビュー作『Cuckoo』も、サイコロジカル・スリラーというサブジャンルの作品として出版されることになった。
しかし、クラウチが2作目、3作目を発表するあいだに、スリラーという呼称に対する違和感が無視できないものになり、ドメスティック・ノワールという造語を考案した。その後、このサブジャンルは、ギリアン・フリンの『ゴーン・ガール』(2012)やルイーズ・ダウティの『Apple Tree Yard』(2013)、リアーン・モリアーティの『ささやかで大きな嘘』(2014)、ポーラ・ホーキンズの『ガール・オン・ザ・トレイン』(2015)などが起爆剤となって絶大な人気を博すようになった。
ワトソンの『わたしが眠りにつく前に』も、クラウチの『Kuckoo』と同じように当初はサイコロジカル・スリラーとして刊行されたようだが、やはりドメスティック・ノワールが相応しいだろう。クラウチのホームページでは、このサブジャンルが以下のように説明されている。ドメスティック・ノワールは主に家庭や職場を舞台にし、主に女性の経験に焦点を当て、人間関係を軸に据え、家庭という空間はそこに住む人々にとって困難で、時に危険な場所にもなりうるという、広くフェミニズム的な視点に基づいている。
ワトソンは男性作家だが、他にトム・ヴォウラーなど、男性も少数ながらドメスティック・ノワールとして認知されている。
『わたしが眠りにつく前に』の物語の語り手であるクリスティーン・ルーカスは、特殊な記憶障害を患っている。毎朝、目覚めるたびに前日までの記憶が失われてしまう。そこがどこなのかも、自分が誰なのかもわからず、同じベッドに知らない男がいるのに気づき狼狽する。年齢については漠然と20代という認識があるため、鏡に映った47歳の自分の姿に愕然とする。激しく動揺する彼女は、夫だという男ベンになだめられ、状況を把握していく。20代のときに事故に遭い、それ以来、夫に頼る生活を送っているらしい。
ベンが仕事に出て、残されたクリスティーンが、これが自分の人生なのかと茫然としていると、夫からコードレスの電話だと教えられた小さな機器からメロディが流れ、ボタンを押して出ると、彼女のことを知っているらしいドクター・ナッシュを名乗る人物が話をはじめる。神経心理学者だという彼の指示にしたがってバッグの手帳を確認すると、彼が「きょう」だという日付(2007年11月30日)に「ドクター・ナッシュと面談」と記されているだけでなく、その下に「ベンに教えてはだめ」とも書かれていた。面談したナッシュの説明によれば、彼女は少し前からベンに内緒で彼の診断を受け、提案にしたがってこの3週間ほどのあいだ、ひそかに日誌をつけていたという。彼女はナッシュが語る前進がどんなものかを確認するために日誌を読みだす。その日誌の最初には「ベンを信じちゃだめ」と記されていた。
本書について特筆すべき点をふたつあげるとするなら、まずは構成だ。「第一部 きょう」「第二部 クリスティーン・ルーカスの日誌」「第三部 きょう」の三部からなり、二部の日誌が全体の大半を占める。第一部できょうがはじまったときは、これまでの日々と同じことが繰り返されるように見えるが、クリスティーンが日誌の存在を知り、第二部で何時間もかけてそれを読んだあとでは、第三部のきょうは第一部のはじまりのような繰り返しにはならない。つまり、一日足らずのあいだに、繰り返されるはずの状況が急展開を見せることになる。
そしてもうひとつは、クリスティーンのキャラクター設定。特に重要なのは、彼女が小説家で、すでにデビュー作を出版し、2作目に着手しようとしていたことだ。第二部の日誌からそのことに関わる部分をいくつか抜きだしてみたい。記憶を失ってはいても小説家として活動していたのであれば、他の職業や主婦業とは経験、関心、感性、こだわりなどが異なり、自分の経験を日誌に記録しようとすることの影響や意味も違ってくる。
たとえば、11月10日の日誌には以下のような記述がある。「(ベンから)『きみは国文科を卒業した』と言われ、目の前にぱっと情景がひらめいた。くっきりと。自分が図書館の前にいるのが見え、フェミニズム論と二十世紀前半の文学をテーマに論文を書こうかと漠然と考えていたことを思い出した。本当は、小説に取り組みながらでも書くことができ、母親には理解できなくてもいちおう妥当と考えてもらえそうなテーマだったからにすぎない。この場面が一瞬宙に浮かんで、ゆらゆら揺らめいた。手で触れられそうなくらい生々しかったが、ベンが口を開くと消えてしまった」
このときは、クリスティーンが小説家を目指していたことを思い出しかけるが、ぼやけて消えてしまう。しかし、3日後の11月13日には、日誌の前日分を読んでいるうちに、もっとリアルで具体的な情景が浮かぶ。その情景はけっこう長いので、最後の部分だけを引用する。
「前回。前回はどうやって書いたの? ダイニングの壁に並んだ本棚に歩み寄り、煙草をくわえたまま上の棚から一冊の本を取り出した。きっと、ここにカギがあるにちがいない。
ウォッカを置いて、両手で本をひっくり返した。壊れやすいものであるかのように、表紙に指先を置いて、そっとタイトルをなぞる。『朝の小鳥たちのために』クリスティーン・ルーカス著。表紙を開き、ぱらぱらページをめくった」
そんな情景に触れて、クリスティーンがどんな反応をするのかは興味深い。「情景が消えた。(中略)いまのは本当なの? わたしは小説を書いたの? 出版されたの? わたしは立ち上がった。膝から日誌がすべり落ちた。だったら、わたしはいっぱしの人間だったのだ。生きがいと目標と野望を持って結果を出した、ひとかどの人間だったのだ」
だが、情景だけでは確信が持てない。だからドクター・ナッシュに連絡し、彼はそれが事実だと認める。その結果、クリスティーンが日誌を書く意味がより明確になる。
「(前略)わたしは真実を知った。自分の力で。教えてもらわなくても、自力で思い出して。いま、それは書き留められた。わたしの記憶ではなく、この日誌に刻みこまれた。日誌の中とはいえ、永遠に。
いま書いている物語――二作目、と誇らしく自覚した――は役に立つものである半面、危険を伴う可能性もあった。作り話ではないからだ。知らずにいたほうがいいことを明るみに出してしまうかもしれない。白日の下にさらされてはならない秘密を暴いてしまうかもしれない。
それでも、わたしのペンは紙の上を走る」
かつてクリスティーンが、「フェミニズム論と二十世紀前半の文学をテーマに論文を書こうかと漠然と考えていた」とき、そのテーマは彼女にとってそれほど切実なものではなかっただろう。だが、自分の物語を書き進めていくうちに、そのテーマが彼女に重くのしかかる。それがどんな場面で出てくるのかは伏せておくが、日誌にはこんな記述がある。そこに登場するクレアは、クリスティーンのかつての友人である。
「(前略)頭にふっと情景が浮かんだ。クレアとわたしが手作りのプラカードを掲げて行進しているところだ。<女性の権利。家庭内暴力に、ノー>と。夫に暴力を振るわれているのに、何もせずに手をこまねいている女性たちを、どんなに自分が軽蔑していたか思い出した。あの人たちは弱虫だ、と思っていた。愚かな弱虫だと。
彼女たちと同じ罠にわたしがはまっている可能性はある?」
クリスティーンは毎朝、目覚めるたび状況に打ちのめされ、怯える。ベンはそんな彼女に、「わかる。でも、心配はいらない。クリス。ぼくがついている。ずっとぼくがついている。だいじょうぶだ。ぼくを信じてくれ」というような言葉をかける。彼女はなにもできない子どものように扱われ、彼に頼って一日が終わり、それが繰り返されてきた。そんな彼女は、自分の物語を追い求めることで、主体性に目覚めていく。それは、女性たちが自分の言葉や物語、声を獲得してきた歴史を想起させる。
本作では、語り手である主人公を小説家に設定したことが重要なポイントになっている。本作を映画化した『リピーテッド』では、日誌がカメラを使った映像日記に変更されているらしい。筆者はそれを観ていないが、日記や手紙、あるいは信頼できない語り手などを多用するドメスティック・ノワールというサブジャンルは、映像よりも活字のほうがはるかに親和性が高いように思える。
《参照/引用文献》
● 『Domestic Noir: The New Face of 21st Century Crime Fiction』edited by Laura Joyce & Henry Sutton (Palgrave Macmillan, 2018)
● “Genre Bender” by Julia Crouch (Blog / August 25, 2013)
● 『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン 棚橋志行訳(ヴィレッジブックス、2012年)
[amazon.co.jpへ]
● 『Domestic Noir: The New Face of 21st Century Crime Fiction』edited by Laura Joyce & Henry Sutton (Palgrave Macmillan, 2018)
● 『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン 棚橋志行訳(ヴィレッジブックス、2012年)
